STORY
ソーシャルワーカーの鴻巣麻里香さん

++ Introduction ++
ご自身の経験をもとに子どもたちの支援をされている鴻巣麻里香さん、
ソーシャルワーカーとして日々活動されています。
ソーシャルワーカーは
困っている人(生活困窮や虐待・暴力の被害、病気や障害など)を
支援する仕事。
個人に働きかけるだけではなく、世間に働きかけていらっしゃいます。
『例えば、いじめがあったとき、いじめられた被害者との間で
心のケアをするのがカウンセラーなら、
ソーシャルワーカーは学校という環境に働きかけ、
被害者が安心して登校できたり、勉強を続けられる仕組みを作ります。
もう一つ、ソーシャルワーカーの大切な役割として
ソーシャルアクションというものがあって
必要だけど、その地域にまだないものを作っていくということ。』
鴻巣さんが活動の拠点を置いている
福島県白河市では
子供が学校以外に気軽に行けるような場所が
以前まではなかったため、立ち上げられました。
必要だけどもないといった環境を変えるべく
日々、ソーシャルワーカーとして活動、
現在は、福島県で、こども食堂とシェアハウスを運営し、
子どもと親子をとりまく様々な社会問題に取り組んでいらっしゃいます。
そんな鴻巣さんがリトルモアから出された新しい本が、
『わたしはわたし。あなたじゃない。10代の心を守る境界線「バウンダリー」の引き方』
タイトルの中にも入っている「バウンダリー」という言葉。
ひとことで言うと「わたしはわたし」「あなたはあなた」という心の境界線とのこと。
『よく私が例えに出すのが「心の皮膚」というイメージ。
心にやんわりと見えない皮膚があるような感じで
皮膚というのは外から良くない刺激が入ってきた時に
私たちの体を守ってくれるわけですよね。
皮膚は外側と隔てるためだけではなく
冷たいとか、硬いとか感じ取れるわけです。
なのでバウンダリーも「あなたはあなた」と隔てるだけではなくて
バウンダリーという皮膚を通して、「あなたってどんな人?」と感じるもの。
私たちがどんな皮膚を持っているかによって
相手からどんな情報が伝わってくるのかっていうのが異なってくる。』
そして鴻巣さんはこの「バウンダリー」は
子どもにとっては、大人になる過程で
とても大事な考え方だとお話ししてくださいました。
『子どものバウンダリーを侵害するもののひとつに、
大人が「昔されて辛かったこと」に意味づけをしてしまい、
子どもに対して同じことを繰り返してしまうということがあります。
「つらいものはつらい」「くるしいものはくるしい」「理不尽は理不尽」
と意味付けせずに自分の中にとどめておくことで、
大人になっても自分を守れるようになります。』
++ Until now ++
鴻巣さんの「一番の辛かった時。」
というキーワードで過去を振り返っていきました。
それは東日本大地震の時に感じたそうです。
発災から1年後くらいの時に被災者支援の現場に入られたとのこと。
そんな中で、先の見えない復興や、放射線などの不安や恐れを
正しい知識で払拭する動きがあったそう。
しかし、不安や恐れの感情になるのは自然であり
その感情自体が間違えと否定されてしまうとそれだけで苦しくなってしまう。
そして不安に対処する方法は人それぞれ異なるため
正しい知識を得たり見通しを立てることで安心できるようになる人もいれば、
不安を持っていることを認められてちゃんときいてもらえることで癒されていく人もいる。
震災の後は後者が軽んじられており、そのことがとてもつらかったとのこと。
この震災で鴻巣さん自身、
改めて考えさせることが多かったとのこと。
『回復よりも復興が優先されたので、
震災の前から何らかの苦しさ(困窮や家庭内暴力)を抱えていた人たちが、
復興の流れに取り残されました。
その後のコロナ禍も同様で、
そういった人々の苦しさは「みんな大変だから」と置き去りにされてしまう。
なので普段から、危機が起きない時から
小さな声が無視されない世の中をつくる必要性を感じた経験です。』
そういった中で、「みんなが大変」という空気が流れている時に
「みんな」に入れてもらえない人がいるというのは
頭の片隅に置いておくのは大事なこととお話をしてくださいました。
現在、ソーシャルワーカーというお仕事をされている鴻巣さんですが
これまでの「うまく生きられない」という経験に導かれて、
ソーシャルワーカーになったとのこと。
鴻巣さんは子ども時代に
外国にルーツがあることを理由に差別やいじめを経験。
いじめがなくなってからも、
人間関係が不安定だったり
自分自身に価値があるのかなど思ってしまい
“生きづらさ”を感じていたそう。
そんな心の中の生きづらさを子供のころから感じつつ
20歳の前半ごろ、精神疾患がある方が集団生活をしている
精神科の医療機関でボランティアをする機会があったそう。
そこで出会った方々も鴻巣さんと同じ
「どうせ自分なんて」と思っていたり
人間関係を築くのが不器用だったそう。
その方々も過去にはつらい思いをしていたとのこと。
そこで自身がうまく生きられない理由が
子どもの頃の「トラウマがかけた色眼鏡」にあることに気が付き、
トラウマを生む世の中を変えるにはどうすればいいか考えているうちに
ソーシャルワーカーになられたそうです。
++ From now on ++
1月17日、1月18日が「共通テスト」のタイミング。
これからの進路に悩む学生さんと親御さん、
それぞれに向けて鴻巣さんは
「今やりたいこと、今好きなこと一番大事にしてほしい。」と
アドバイスしてくださいました。
『いつも将来のことばかり考えていますが
将来って、今ここにないんですよね。
まだ来ていないもののために、
今あなたが大切にしているものを我慢するって
本当にそれは良いことなのかなという風に思います。』
でも、今好きなこと・やりたいことがわからないことは当たり前
なので探すこととして一旦、大学へ行ってみるのもありだと
鴻巣さんはお話ししてくださいました。
大学は、いろんな情報や人、学問に触れる体験ができる
有意義なものなので
どんな環境に置かれている子供でも
アクセスできる場所であってほしいとのこと。
現在では大人も子供も関係なくSNSを見る世の中ですが
しかし、そんなSNSがあることによって
家の中でも、外の関係が入り込んでしまう。
そうすると疲れた心を癒すために大事な
1人で自分と向き合う時間がSNSによって奪われてしまうので
SNSネイティブ世代の子供たちは疲れやすいのではと
教えてくださいました。
なので改めて、1人時間をちゃんと持てているか
お子さんと一緒に考えていくのが大事とのこと。
ソーシャルワーカーとして活動されている鴻巣さんですが
そんな鴻巣さん自身の早期引退が夢なんだとか。
『ただこれは仕事が嫌いだとかじゃなくて
歳をとっていくとどうしても価値観のアップデートが鈍ってきてしまう
すると今私が関わっているのが
大体10代後半〜20代くらいの方々がメインなので
彼らが見てきた世界と、
私が見てきた世界少しづつズレが生じてきてしまう。
私はずっと現場にいたいんだけど
価値観のアップデートが鈍ってきた人間が
ずっと現場にいて、声が大きくなっていくというのは
望ましくないなと思っているので
30代くらいから自分の終わりを決めて
自分から引いていこうとという風に考え始めて
そろそろ実行に移していかないとなと。
後進を育てつつ、自分の次のキャリアを考えたり。
そうすると、これまでやりたかったことが後回しにしていたことや
今したいことをもう一回大事にしてみようかなと思い
いろんな新しいチャレンジを始めてます。』
ON AIR LIST
-
 KIND AND GENEROUS / NATALIE MERCHANT
KIND AND GENEROUS / NATALIE MERCHANT -
 BELIEVE IN LIFE / ERIC CLAPTON
BELIEVE IN LIFE / ERIC CLAPTON -
 OVER WHEN IT'S OVER / LUCY ROSE
OVER WHEN IT'S OVER / LUCY ROSE




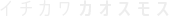


ナビゲーターのトークコラム的コーナー「イチカワカオスモス」では
リスナーの皆さんから届いたメールをご紹介!