





「明けましておめでとうございます。坂本龍一です。今年もRADIO SAKAMOTOを、よろしくおねがいします。2012年の元日。みなさまは、いかがお過ごしでしょうか。去年── 2011年といえば、ほんとに "3.11" ……災害のことがやっぱりいちばん大きくて、ずーっとそういうことを考えてきて、あっという間に1年が終わってしまったような感覚がありますよね。いつもにも増して、早い1年だったような気もしますけど、もちろん問題はいろいろ山積みです。まあ、"Life Goes On" と、いうことですね。あのー、その軽々しく、"今年は良い年に" ……とかね、簡単にその、バラ色の世界のことは、もう口にできない。やっぱりいろいろ世界を見渡しても問題だらけだし、経済のこともね、いいニュースというのがないですけどもねぇ……。ほんとにね、個人個人が少しでも、健康に気をつけて、より良い生活を送るように努力するしかないですね」
「さて、今回のRADIO SAKAMOTO は『お正月スペシャル』です。三人の論客を迎えて、2012年の世の中……あるいは10年後、20年後の社会をね、20年後って言ったって、いま生まれた赤ちゃんが二十歳になるときですからね、そんなに先ではないですよ。"20年なんてあっという間に来ちゃうよ" と、いうそう時間のスパンで、より良く生きていくためのヒントを見つけていきたいと思います。」
▼ゲスト:慶應義塾大学経済学部教授・金子勝さん
<この国にいちばん合わなかったのが原発だった>
おひとりめのゲストは金子勝さん。
慶應義塾大学経済学部教授
Twitter アカウント (@masaru_kaneko)
「きょう、金子さんに来ていただいたのは原発問題も怒り心頭なんですが、もう少し大きく世界を見てね、本でも書かれてらっしゃるんですけど、現在の世界って非常に危うい世界だと思うんです。それを "経済学者" という目から見て、わたしたちは、どういう危機を持っているのかっていうのを簡単に言ってくれませんか。」

「あのー、なかなか実感が掴めないと思うんですけど、日常生活は昨日と今日が連続してるんで、だけど起きてる……例えば、グリーンスパン元FRB議長が「100年に一度の経済危機」って言ったじゃないですか。100年だから、まだ続いてるんですよね。現在のユーロ危機もその延長なんです。リーマンショックで、やばいというか、毒入りの証券化商品を銀行が持っちゃって、今も隠れて不良債権が貯まっちゃってるんですね。これは日本の20年前と同じで。で、結局、買う物がない、投資する先がない、融資先がないから、国債買うわけです。で、みんな経済を支えようとして、財政赤字だして、景気対策やる、公的資金入れる、で、今度、弱い国の国債も持つ訳じゃないですか、他に買うものないから。で、これが格下げになって、やばくなってくると、持ってる銀行もやばい、ってなるじゃないですか。で、伝染していくんですよ。これって不思議なんですけど、医学も人体の血液がほんとに解らないように、文学とかも最後は説明ができないのと同じところがあるんですよ。経済でも、お金とか銀行の話っていうのも、説明がつかないんですよ。一番肝心なところが説明つかないのは、お互いがお互いに信用できないと経済は持たない、っていうことなんですよね。聞いた話ですけど、子どもが成長するなかで "ひとにあげる" っていうのはできるようになるんですって。あと "買う" っていうのもできるようになる。でも "貸す" っていうのは、できないんですって。つまりお互いを信用し合わないと、相手が返してくれるっていう……相手の人格を信用したり、さまざまにお互いを信用するっていう、"貸す" という行為が、いちばん最後に覚える行為なんだそうです。」
「もしかしたら、人間の本能では難しいから、貨幣制度なんかに置き換えて、信用をフォーマライズしてやってるのかもしれませんね。」
「後ろに国とか、中央銀行とかいう、巨大な、絶対的に信用できそうなもの。で、むかし地方銀行が銀行券を発行してるときも、すごい名望家がやってたんですよ。地域でいちばん信用がおけるひと……名家であるとか、お金持ちであるとか。だから "あのひとは最後は絶対払ってくれるだろう" っていう信用。それが、世界的に壊れてるっていうことなんですよ。」
<持続可能なエネルギーと経済>
「大嵐の中の、木の葉のような日本……東日本の復興なんか、全然まだこれから何年もかかると思いますし、原発事故も首相は収束宣言って言ってるけど、とんでもない話だし、だけどその、危機がたくさんあり過ぎて、どうしたらいいのか解らないんですよね……。金子さんは、どこかに希望はありますかね。」
「ぼくはあんま絶望してないんですよ。日本人て、10年もすれば忘れちゃうだろっていうのが普通じゃないですか。だけど、例えば戦争の直後30年くらいは、"戦争いやだ" が多数派だったじゃないですか。たぶんね、命とか健康とか言っちゃうと、こう何ていうのかな……これ以上、説明できない、この後は非論理の世界になっちゃうので、……ちょっと不謹慎ですけど、水前寺清子の「三百六十五歩のマーチ」みたいで、例えば、一見、後戻りするようだけど、三歩進んで、三歩は下がらないと思うんですよ、日本は。そこが、僕は最後の出発点で、日本のひとを信じているんですよね。そしたら原発に代わるエネルギーを作ろうよ、っていう話は、当初、すごくこんなの現実的じゃないっていうのは多数派だったんですよ、原発事故直後も。それが代替エネルギーなんかも注目されてきて、これを、こういう動きを食い止めたいと思っている古いひとたちも、だんだん少数派になってるんですよ。そのときに、すごく出だしが大事なんだけど、再生可能エネルギー、いわゆる自然エネルギーは、初期は高くて不安定だから導入しない、って言ってるんですよ。だけどもうドイツは去年、原発よりも再生可能エネルギーの方が率が高くなったんですよ、逆転が始まった。現実に、実例があるじゃないですか。そうすると僕らが、太陽光とか風とかで生きてくなんて無理だろと思ってたのが(笑)、もうひとつの力になる。そして、買い取り価格を高くすれば、間違いなく、みんな投資するんですよ。例えば「電卓」なんて、昔は1万円以上したんですけど、いまはもうちょっとした値段でいいもの買えるじゃないですか。量産するとコストも下がる訳です。そうすると、初期の段階でばーっと作って普及さえできれば、急激に下がってくる。」
「金子さん、僕はこんなにたくさんの人が住んでる、この "都市" っていう形態が、けっこうバッド・デザインだなと思いだしていて、"脱都市" っていうのが、これから始まるような気がしてるんですよ。つまり情報とモノがどこにいても来れば、こんなところにみんなで固まって住んでる必要がない訳じゃないですか。割と小さなコミュニティで、食とエネルギーを自給できて、そういう小さなコミュニティーがネットワークで繋がってるのが理想だと思うんですよね。」
「たぶん、金融資本主義が終わって、なんかこう……公共的なものに貢献することで生きていくっていう、所得を得たり仕事を作ってく。"公共性" って言うと飯奉公みたいに感じるのが日本人なんだけど、もっと言うと社会的ニーズに合わせて、人に喜ばれることをやっていくことの方が長続きするっていう、人をバブルで出し抜いて騙す経済じゃなくて、何か役に立ってることによって当然の報酬を得てる感覚っていうのが、人間の人生がおかしくならないっていうか。お金に溺れず、何か自分のやっていくことの意味みたいなものについて、ミッションだとか、どこかそういうものを、スープの出汁のように抱えてないと、やっぱ長続きしないんじゃないかと思うんですよ。」
「やっぱり、どんな奴でも、"いいこ、いいこ" されたいんですよ、褒められたいんですよ。だからミュージシャンだろうが、金融のひとだろうがね、やっぱり人に喜ばれて、嬉しいはずですよ、きっと。しかもそれでビジネスになるんだとしたら、こんな良いことはないですよね。自分も嬉しくて、ひとも嬉しくて。」
「"この歌を聞いて、自分は人生でこういうこと考えた" とか言われると、なんか考えてもいないような反応があるときってあるじゃないですか。僕も本書いててあるんですよ、そういうときは書いて良かったなっていう。そういう時はもう、印税とか関係なくなってるんですよね。」
「少しでも売れた方がいいですけども(笑) でも、そのためにやってるわけではないですものね。」
「たぶん、この原発事故からエネルギー転換の中で、そういう倫理の転換というか、経済学、社会学では "エートス" って言うんですけど、経済を支えている精神とか倫理とかが、じわじわ変わっていくような気がしているんですよ。環境だけが持続可能じゃなくて、経済も持続可能になってきて、ひとがハッピーになっていくんだと思うんですよ。この国にいちばん合わなかったのが原発だった。それが解っちゃったんだと思うんです。もう一回、舵切り替えれば、向いてないもの止めた方がいいんですよ。……大変だけど、三歩進んだら、二歩までしか下がらないから、やっぱ "正しい" っていう感覚が、いいでしょう。楽しいでしょう。後ろめたい気持ちがあるわけじゃないから、すっきりしてるんですよ、僕はね(笑)」
「ここまで来たらね、底をついてますからね、上がるしかない。ありがとうございます。(拍手)……とても良い話、聞かせていただきました。なんか希望の……ちょっと明るいなあ。明るい気持ちになってきた(笑)」
▼ゲスト:ASIAN KUNG-FU GENERATION・後藤正文さん
<THE FUTURE TIMES>

「こんばんは。ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文です。きょうはですね、坂本龍一さんがお送りしているRADIO SAKAMOTOにお邪魔しまして、わたくしが編集しています、『THE FUTURE TIMES』というフリーのニュースペーパーの取材をさせていただく、という主旨でお邪魔しました。よろしくおねがいします!」
「どうも、ゲストの坂本でーす!」
──ということで続いてのゲストは、ロックバンド:ASIAN KUNG-FU GENERATIONのボーカル&ギター、後藤正文さん。後藤さんが編集長を務める、新聞『THE FUTURE TIMES』に掲載するためのインタビュー取材を、RADIO SAKAMOTOのなかで行なっていただきました。
<じゃあ、新聞屋になってみようかなみたいな。音楽家として。>
「創刊号を、わたし作ったのですけれども、そちらで『LIFE311』ですね、(岩手県気仙郡) 住田町の取材をさせていただきまして、ほんとに素晴らしい取り組みで……坂本さんは以前から『more trees』の活動をされてるじゃないですか。恐らく僕らの世代に比べて10年ぐらい早く、そういう取り組みを始められてると思うんですけど。僕も、この震災の前から原発問題を調べ始めたんですけど……」
「僕もミュージシャンですけども、ミュージシャンでは珍しくないですか(笑)」
「そう……ですね、珍しかったですね(笑) で、そういうことを日記に書き始めると、決まった反響が……"おまえら電気使ってるだろ" っていうのが最初に来たんですけども。」
「僕も90年代、最初にCDのパッケージを換え始めたときからですね、"ちょっと坂本、頭おかしくなった" とかですね、結構コアなファンが引きましたね。面白いですね。でもそれが、世の中の空気が変わったのが2001年過ぎてからですかね、そういう環境の雑誌も出てきたりとか、いまや、エコなコンビニなんかもありますからね、隔世の感がありますけれど。ただやっぱり、事故の前までは、原発の問題なんていうのは、比較的タブーな雰囲気がね、あったと思いますけどね。」
「不思議だったんですよ。いろんなことに興味を持って、こう……調べていくとなんかね、坂本さんがいらっしゃるんですよね、いつもね。不思議なんですよ、例えば、縄文時代に興味を持って調べていくと、また坂本さんがいたり(笑)。今回も『THE FUTURE TIMES』の取材先を探したり、友達とかと話しているときに、例えば、"四国に面白いところがある。檮原(ゆすはら) って言うところなんだけど、そこは自給自足でエネルギーを供給していて……" で、よくよく調べていくと、あ…… "more trees" の森だ、みたいな。」
「すいません。目の上のタンコブだ(笑)」

「個人的には、原発問題とかに行く前に、日本の若いロック・ミュージシャンが、どうして、社会とか戦争とかいうものだったりにコミットしていなかいのかっていうのを、とても不思議に思っていて、僕も歌詞に書くべきかどうか、っていうか、やり方が解らないっていうのもあるんですけど、発言していくべきか、って考えている時期があったんですけど、たまたま書店で坂本さんが表紙の雑誌を見つけて、タイトルが「反対しないと戦争はなくならない」っていう、その記事を読んで、かなり勇気をもらったっていうのがあるんですけど。……気が楽になりましたね。ロック・ミュージシャンなんだから、気にしないで言えばいいんだっていう。ま、そういうところから、だんだんこう、原発の問題とかも踏み込んでいくようになって、この『THE FUTURE TIMES』に至ったんですけど。」
「悪い影響を及ぼしているのかな、はっは(笑) ……もともとはロック・ミュージシャンなどは、普通の人よりも早く、そういうことは気になって、しかも社会に対して意見を言うと……いう人たちだったはずなのに、60年代、70年代なんていうのはそうですよね。そういう伝統は、欧米では、まだ減ってなくて、もちろん社会的な発言はクールじゃないみたいな世代も居ますけどね。日本は "民主主義" 自体も、占領軍によって上からぽんともらっちゃったもの。で、ロックも輸入品ということで、やっぱ根付いてないのかなっていう(笑) まあ、いま根付く過程の中にいるのかな、という感じはありますけど、根付いていくのは時間がかかるんだと思うんで、あのような悲劇が、2011年に日本にあって、これを大きなきっかけにして、別にロック・ミュージシャンに関わらず、誰でも自由に自分の意見は言える社会になった方がいいと思いますよね。」
「なかなか僕らの世代って、あんまり社会とコミットしないのがクールというか、良しとしてた時代が。だから、デモとかも、ちょっと冷めた目で見てる人が多い。で、僕も最初はそうだったんですけど、だんだんやっぱり、あれは行かなきゃいけないよっていう、まあ、ものもいっぱいあるんで……」
「まあ……あの若者だけが楽しそうに "ジャカジャカ音楽を演りながらやる" っていうのも、ちょっといかがなものかなっていう気もしてます、僕は。というのは、例えば、今回の原発事故を受けてのデモだとしたら、いちばん被害を受けている福島のおじいちゃん、おばあちゃんたちが、簡単に入れるようなデモってなかなか無いでしょう。やっぱり意識が高い人とか若者は行きやすいけど、いちばん困っているひとたちは自分たちの意見を言いやすいようなデモとか集会っていうのが、なんか無いような気がしてるんです。だから、それはあった方がいいなと思ってたりとかね。」
「この『THE FUTURE TIMES』は、若い世代が……自分たちを含めて、もう少し社会に対して大きい声をあげるっていうよりは、自分たちの、日々の選択の質を高めるというか、そういう意味で社会にコミットしていくというか。例えば、いい物を買うとか、いいエネルギーを選ぶとかっていうことでしか、変わらないと思うので、歩かないデモがあってもいいんじゃないかと思ったんですよね。最初の発想はそこで、一応、ミュージシャンの端くれとして、ミュージシャンがニュースペーパーの役割をしていた時代とかもあって、それもひとつのヒントだったんですけど。じゃあ俺、もう一回、新聞屋になってみようかなみたいな。音楽家として。」
▼ゲスト:作家・竹田恒泰さん
<2012年は『古事記』完成から1300年。>

最後のゲストは、作家の竹田恒泰さん。竹田さんは、慶應義塾大学で「憲法学」の授業を受け持たれています。日本国憲法第1条「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」この第1条が日本人にとってどういう意味があるのか、これを1年間かけて教えていくそうです。年間の授業の1/3を「日本神話」に当て、そこから日本の歴史、天皇の統治〜帝国憲法から現憲法に移っていくようすを踏まえ、条文を勉強するそうです。古事記を訳した『現代語古事記』を出版されたり、エネルギー問題にも詳しく、『原発はなぜ日本にふさわしくないのか』なども書かれています。
<保守とは、なにを "保守" するのか。>
「実は、今年 "古事記1300年" という年回りに当たるんですね。平城京遷都が710年、その2年後の712年に古事記が完成してますので、2012年というのは、古事記完成1300年の年回りなんです。なんかこれ僕、意味があるんじゃないかと思ってまして、昨年が地震で、今年が古事記ですよね。で、来年が「式年遷宮」……この流れっていうのは、何もないときに来てもですね、ふーんで終わっちゃうんですけど、大震災を経験して、日本人が "日本人とは何か" と思っているとき、何か意味があるんじゃないかなと思います。」
「僕がね、そもそもなぜ竹田さんに興味を持ったのかというと、著書『原発はなぜ日本にふさわしくないのか』を2011年に出されて、ほんとうにお詳しいですよね。原発の問題は話が尽きないんですが、竹田さんは、明治天皇の玄孫ということで。竹田さんが考える "保守" っていうのかな、日本の在り方。まあ、女帝の問題も含めて……」
「保守って "何を保守するか" っていう話じゃないですか。僕が考えている保守というのはですね、日本人そのものが、とても輝いていた時代がある訳ですね。今はその、輝き方が、違う輝き方になってきてしまっているんですけれども、僕のいちばん輝いているって言ってるのは "幕末" なんです。ここがですね、日本文明が最高に、頂点を迎えた瞬間で、ペリーが来航して、ハリスという外交官がアメリカからやって来て、ハリスが手記に残してるんですけども、最初、まだ江戸に入れなかったときに、下田に着任したんですね。そのとき、周辺にいた人たち、彼の言葉で言うと、社会の底辺のひとたち。漁師とか農家であるとか……が、貧しそうに見えるし、確かに貧しいんだろうけども、身なりはちゃんとしていて、礼儀正しくて、寂れた感がどこにもない、と。社会の底辺のひとたちがこれほど豊かに暮らしているというのは、恐らく世界で日本しかないだろう、ということを言っているんですね。それから、よく外国人に言われたことなんですけど、普通、"衣食足りて礼節を知る" という、だから、衣食が足りないひとは、荒んでしまって、礼儀とか徳とか、そんなものは出てこないというのがヨーロッパの常識らしいんですが、日本人は社会の底辺の人までもが、生まれながらにして "帝王の徳" を持っていると。ですから日本人の感覚で言うと、それは当然で "衣食足らずとも礼節だけは汚さない" っていうことがあるじゃないですか。日本人の持ってる気質っていうのは、とてもすごいものがあると、僕は思うんですね。例えば、釈迦が唱える中道にせよ、孔子が唱える中庸にせよ、右でも左でもない、ちょうどバランスよく真ん中っていうのは、和の精神だと思うんですけど、これって聖人君子は言ってるんですが、民族単位で実行してた人がいるのか、っていうと、基本的にないですね。そういう日本人のほんとの輝き、これを大切にして、次の世代に受け継いでいくっていう、これが僕のいう "保守" なんですね。」
「日本がそういうとても珍しい国民性を持った、っていうのは、なぜでしょうね」
「ひとつの要素として、古事記が挙げられると思うんですよ。先ほど1300年と言いましたけど、古事記の中で「国譲り」の物語がありますね。最初に、なんかもう "国を譲るなんて嘘だろう" と思われていたんですけども、出雲周辺の発掘が進んでくると、これは恐らく史実だったのだろうということが解ってきまして、つまり出雲にはちゃんとした軍事国家があって、独特の宗教文化があったらしいんですね。で、これがですね、戦争の形跡が見えない……らしいんですね。戦争なくして国がひとつになっている。今も出雲大社が存在している訳ですよね。で、恐らくこれは出雲だけでなくて、周辺の諸国もだいたいみんな "話し合い" でまとまってきたと。これも日本全土の発掘の結果ですけども、4世紀に統一王権ができたということが、ほぼ確実に言われているのですが、4世紀を通じて大きな戦争の跡がどこにも見えないらしいんですよ。ということは世界史でですね、"戦争を経ずして統一国家ができる" なんていうのは、ちょっと他に僕は聴いたことがないですね。やっぱり日本人というのは太古の昔から、和の精神、話し合いの精神があったんだろうなと思うんです。で、その時から皇室があって、天皇があって、その天皇自体を攻め滅ぼそうと思った人は、これまで2000年、いない訳でして、そういう日本人の精神を象徴するかのような存在、中心軸があって、そのままずっと日本人はですね、太古の昔からの大自然との調和、人と人との調和、こういったものを大切に育んできた、そういうのが日本人なんじゃないかなと考えているんです。」
<日本は "和の国" だということ。>
「ま、この日本列島という風土と、そこに暮らしてきた日本人。ま、どういう存在で、これからどういう方向に歩んでいこうとしていることをね、この国の形をどうしようとしてるのか、ということを、最大に問われている時だと思いますね。残念なことに、政治家もビジョンを指し示すことができてない訳なんですけど、竹田さんが考える日本はこういう方向に進むべきだという、エネルギー問題とかも含めてですね、ビジョンはお有りですか。」
「やっぱり日本は "和の国" ですから、人と人との和、最終的には外国との和から大自然との和まで、そういったものを鍛錬してきてると思うんですね。外国との和と言ってもですね、一見、日本の外交は三流とか四流とか言われますけど、僕は実際はそうでなくて、世界中から日本が愛されているっていうのを感じていて、日本人て、外国人からすごく慕われていて、ま、これ外交だけの力じゃないですけど、日本そのものが外国人から関心を持たれるような道を歩んできてると。で、そうすると日本は和の国ですから、大自然との調和もそうですし、最近はTPPとかも議論されてますけど、この日本の為うんぬんというよりも、例えばアジアの国々が輝く、というイメージを持ってですね、その中で日本が何ができるのか、で、周りの国が輝ければ、更に輝ける。周りがボロボロに衰退していって日本だけがなんていうことはあり得ない。これが "和" だと思うんですよね。」
「ちなみに "和" というのは、英訳すると何になるんですか。"harmony" ですか、難しいでしょう(笑)」
「難しいですね。英訳ですか、ちょっと参考になるか解らないんですけど、中国の孔子がですね…… "和" と "同" の違いをこういう風に言っているんですね。和というのは "自己の主体性を保ちながら、他者と協調すること" だと。で、同というのは "自己の主体性を失って、他者と協調すること" だと。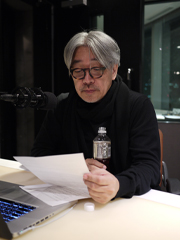 だから、和と同は似て非なるものだということですね。例えば "harmony" なんですけど、いざというときにハーモニーを乱してまでも、言わなきゃいけないことがあったりとか。だから "harmony" は、同の方に近い気がしますよね。この "和" は、日本にしかないんじゃないですかね。」 だから、和と同は似て非なるものだということですね。例えば "harmony" なんですけど、いざというときにハーモニーを乱してまでも、言わなきゃいけないことがあったりとか。だから "harmony" は、同の方に近い気がしますよね。この "和" は、日本にしかないんじゃないですかね。」
「エネルギー問題なんかは、どうですか。」
「国としての独立を維持するためには、軍事的な安全保障だけではなくて、食料とエネルギーの安全保障も必須ですよね。よくあの、原発がなくなったら日本は経済衰退するとか言いますけど、あれもう嘘ですから(笑) ……最新鋭のコンバインドサイクル発電を使えば、半分の燃料で同じ電気が作れます。しかも工期や金額が、原発の1/10という。古い火力発電所をコンバインドサイクル発電に変えていけば、今の数値を維持しながら原発を廃止できますね。」
|
■「現代語古事記」、「ソーシャルメディアの夜明け」、「いまだから読みたい本。3.11後の日本」をセットで2名様にプレゼント!
RADIO SAKAMOTOからのプレゼントです。
今回は、お正月に本を沢山読んで頂きたい、ということで、まずは、ゲスト竹田恒泰さんの著書「現代語古事記」、そして、教授のUst中継ではおなじみ、デジタルステージ代表・平野友康さんの最新著書、「ソーシャルメディアの夜明け」、そして、坂本龍一さんとその仲間たちが編集した、「いまだから読みたい本。3.11後の日本」を、セットで2名様にプレゼントします。
番組の感想やメッセージも、ぜひお書き添えのうえ、コチラからご応募ください(教授と番組スタッフ一同、楽しみにさせていただいてます)。当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます。
|
|
|



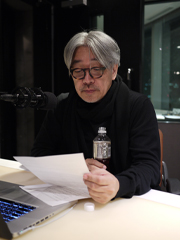 だから、和と同は似て非なるものだということですね。例えば "harmony" なんですけど、いざというときにハーモニーを乱してまでも、言わなきゃいけないことがあったりとか。だから "harmony" は、同の方に近い気がしますよね。この "和" は、日本にしかないんじゃないですかね。」
だから、和と同は似て非なるものだということですね。例えば "harmony" なんですけど、いざというときにハーモニーを乱してまでも、言わなきゃいけないことがあったりとか。だから "harmony" は、同の方に近い気がしますよね。この "和" は、日本にしかないんじゃないですかね。」




