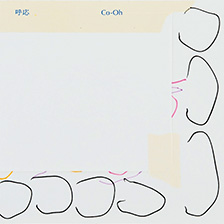<今回のナビゲーターは、編集者の鈴木正文さん。>
「坂本龍一さんが2ヶ月に1度お届けしている、J-WAVE レディオ・サカモト。今回の放送も、坂本さんが病気療養中の為、お休みとなります。代わりに、この編集者の私である鈴木正文がお届けいたします。えっとまずは、恒例になっているみたいなんですが、坂本さんからメッセージが届いています。」
スーさんとは『音楽は自由にする』を作るときに、
話し相手になってもらい、とてもお世話になりました。
元々、スーさんと話すのが楽しく、話がはずむので、
今回の『新潮』の連載でもスーさん以外の話し相手は考えられませんでした。
なぜスーさんと話すのが楽しいのか。
一つは世代が近いので、60年代の昔のこともツーカーで話が通じます。
そしてスーさんはとても頭がいいので、どんな話題にも的確に、
時にはこちらがとてもインスパイアされるような反応が返ってきます。
そして二人とも考え方がリベラル、またグローバルなので、
世界の見方も近いところがあります。
というような理由で、スーさんと話しているととても楽しいのです。
今回は僕の代わりに番組を担当してくれることになりました。
どうかよろしくお願いします。
|
|
 「ちょっと代読させていただきます。「スーさんとは」って、スーさんってすいません、あの、僕のことなんですね。鈴木なんで。あの、坂本さんいつも僕のことスーさんって、呼んでくださっています。「スーさんとは『音楽は自由にする』を作るときに」、この音楽は自由にするっていうのは、えっと2009年に新潮社から出版された、坂本さんの自伝本です。で、その時、僕は編集を担当したひとりでした。ということで、もう1回あたまから読み直しますと……「スーさんとは『音楽は自由にする』を作るときに、話し相手になってもらい、とてもお世話になりました。」いいえ、とんでもございません。「元々、スーさんと話すのが楽しく話がはずむので、今回の『新潮』の連載でも、スーさん以外の話し相手は考えられませんでした。」この今回の新潮の連載についてはあとでお話いたします。「なぜスーさんと話すのが楽しいのか。一つは世代が近いので、60年代の昔のこともツーカーで話が通じます。」確かに。「そしてスーさんはとても頭がいいので」いいえ、そんなことはありません。「どんな話題にも的確に、時にはこちらがとてもインスパイアされるような反応が返ってきます。」これは買い被り……だと思います。「そして二人とも考え方がリベラル、またグローバルなので、世界の見方も近いところがあります。」だといいんですが。「というような理由で」って、いちいちなんかツッコミ入れててすいませんね(笑)。「スーさんと話しているととても楽しいのです。」ありがとうございます。「今回は僕の代わりに番組を担当してくれることになりました。どうかよろしくお願いします。」もうとんでもないです。坂本さんの代わりは、とても務まらないんで、えっとちょっと今、暗澹たる気持ちが若干なんか胸の辺りを走りましたが。えーというようなメッセージをいただいております。で、またこの番組にお帰りになることは確実なことだと思いますので、ぜひその間、このレディオ・サカモトを含め、注目していただきたいと思います。」
「ちょっと代読させていただきます。「スーさんとは」って、スーさんってすいません、あの、僕のことなんですね。鈴木なんで。あの、坂本さんいつも僕のことスーさんって、呼んでくださっています。「スーさんとは『音楽は自由にする』を作るときに」、この音楽は自由にするっていうのは、えっと2009年に新潮社から出版された、坂本さんの自伝本です。で、その時、僕は編集を担当したひとりでした。ということで、もう1回あたまから読み直しますと……「スーさんとは『音楽は自由にする』を作るときに、話し相手になってもらい、とてもお世話になりました。」いいえ、とんでもございません。「元々、スーさんと話すのが楽しく話がはずむので、今回の『新潮』の連載でも、スーさん以外の話し相手は考えられませんでした。」この今回の新潮の連載についてはあとでお話いたします。「なぜスーさんと話すのが楽しいのか。一つは世代が近いので、60年代の昔のこともツーカーで話が通じます。」確かに。「そしてスーさんはとても頭がいいので」いいえ、そんなことはありません。「どんな話題にも的確に、時にはこちらがとてもインスパイアされるような反応が返ってきます。」これは買い被り……だと思います。「そして二人とも考え方がリベラル、またグローバルなので、世界の見方も近いところがあります。」だといいんですが。「というような理由で」って、いちいちなんかツッコミ入れててすいませんね(笑)。「スーさんと話しているととても楽しいのです。」ありがとうございます。「今回は僕の代わりに番組を担当してくれることになりました。どうかよろしくお願いします。」もうとんでもないです。坂本さんの代わりは、とても務まらないんで、えっとちょっと今、暗澹たる気持ちが若干なんか胸の辺りを走りましたが。えーというようなメッセージをいただいております。で、またこの番組にお帰りになることは確実なことだと思いますので、ぜひその間、このレディオ・サカモトを含め、注目していただきたいと思います。」

<坂本龍一、自伝の連載「ぼくはあと何回、満月を見るだろう」について>
「坂本さんのメッセージにもありましたが、坂本さんとは、ちゃんとお話したのは2000、2001年ですか、いわゆる911がニューヨークで、いわゆる同時多発テロがありまして。で、その際に坂本さんが『非戦』っていう本をその後にですね、坂本さんのえっと、知人、友人関係の中で、あれを契機にですね、イスラムの過激派の勢力との戦争なりなんなりっていう、何か戦争的な事態が、そして実際に戦争が始まるわけですけども。そこで、その態度表明された本、ご本が出たのがきっかけになって、僕はニューヨークに取材に行ったんですね。で、そのとき僕は、新潮社から『ENGIN』という、今でも出てる雑誌があるんですが、その編集長でしたので、その辺からのお付き合いだったと思います。で、そのENGINで、実はさっき出た『音楽は自由にする』っていう書籍が、2009年に新潮社から、坂本さんの本格的な初めての自伝ということで、それをうたって出版されたんですが、その本の元になったのは、月刊誌のENGINで連載していた、まぁ自伝シリーズ。それこそ、『音楽は自由にする』っていうものに、その連載が結実したんですね。これはまぁ坂本さん誕生の、幼少の見入りからですね、一番最初に作曲したのが、「ウサちゃんのうた」っていう、そういう曲だったようなんですが、まぁその辺の事情からですね、まぁ皆さんご存知のケータイ時代からYMO時代を経てですね、独立して、で、アカデミー賞音楽賞を獲る。さらには、ニューヨークに活動の拠点を移してですね、もう皆さんご存知の大活躍をされる。2009年に至るまでのことを、その本で坂本さんが振り返ってまとめております。で、その担当の編集者で、その時に、お話し相手としてですね、いろいろな楽しい会話とか、考えさせられる論点を一緒に考えたりとか、まぁそういうことをしてきたんですね。で、それがですね、えっと、今年になって、坂本さんあの、皆さんご存知だと思いますが、中咽頭がんっていう、あの、がんを2014年に発症しまして、それは寛解したんですけれども、その後、2020年のですね6月に、直腸がんがあるっていうことがニューヨークの中咽頭がんを治療した病院で、まぁある程度定期的に検査をしてた、というふうに聞いておりますが、まぁそれが発見されたんですね。で、まぁそれも普通に治していこうと、いう風にお考えになって、音楽を含めた社会的な活動まで含めて、音楽とか文化的な活動はお続けになって、その2020年といいますか、まぁ2年前なんですが、ちょうどに世界をコロナが襲い始めた年ですね。えっと、東京に……11月ぐらいにですね、いろんなお仕事の関係で来て、念の為に、それだけじゃなくてチェックをしたところですね、実は直腸にがんが発生してますよ、ということが分かったんですね。で、そのとき一番最初に診ていただいたその病院では、このままでは余命がまぁ半年ぐらいじゃないですかっていう、非常にショッキングなことを告げられて、でまぁセカンドオピニオンっていうのと、いっていいのかどうかあれなんですが、また別のあのところでも検査をして、で、いろいろな問題点が発覚したんですね。実は直腸だけではなくて、様々なところに転移があるというようなことで、2021年の1月からですか……大変困難な手術を経験されるという、そういう事態が起きたわけです。その辺のことについては、あの、再度がんが見つかりましたっていうことは、短い発表文みたいなものは当時流されまして、でもまぁ頑張ってがん治療にあたりつつ、仕事も続けていきたいと思います、というようなリリースあったんですが、まぁあまり詳しいことは、実際病状についてもいろいろ複雑な事情もありましたし、明らかにされていなかったんですが、そのことを含めまして、『新潮』という、まぁ純文学系の文芸誌、非常に古い文芸誌があるんですけれども、その7月号、6月7日に発売されたんですが、7月号から、「ぼくはあと何回、満月を見るだろう」という、そういうタイトルの連載が始まりました。で、その連載の第1回目で、がんとの闘いですね……直腸に原発巣があって、それがいろんなとこに転移をしてですね、最初の大手術が21時間に及んだということ、だったようです。ちょっと想像することができないぐらいの、大変な大手術で。で、その後も2021年、つまり昨年ということになりますが、何回か小手術含めて、あるいは中手術も含めてありまして、今年に至るまでも、時間を置きながらですね、そういう状態が続いてて、現在治癒中と。で、新潮でのその連載っていうのは、第1回目はその闘病の話ですが、その後も今まで3回やっておりまして、4回目が9月7日の発売の新潮に載る予定ですので、えーもうじきですね……皆さんもお読みになることができるかと思いますが。2010年からの坂本さんの音楽的な歩み、あるいは様々な音楽にとどまらない、今インスタレーション、設置音楽っていうような形でも、非常に活発な活動をされてきておりますし、映画音楽も無論ですが、さらには社会的な活動であったりとか、音楽に関わりつつも、例えば東北ユースオーケストラであるとか、more treesの活動であるとか。その多彩な活動はずっと続けてこられてるんですが、そういうことにも触れつつですね。大変興味深い連載が行われています。ぜひチャンスがあったら、ご参照していただけると、と思います。」
「で、えっとまぁそういうことなんですが、じゃあ、その連載のタイトルはなぜ「ぼくはあと何回、満月を見るだろう」っていう、非常に印象的なタイトルなんですが、になったのかということについて、今日はちょっとお話したいと思います。えっと、今年に入ってですね、2009年でまぁ自伝本が終わってるので、もうあれから12〜13年経ちました、と。で、もう1回だから、そういう意味では「音楽を自由にする」っていう、いわば続編として、坂本さんの活動を振り返ろうと、人生の軌跡を振り返ってみてはどうか、というような話が持ち上がって、まぁ坂本さんサイドと打ち合わせをしたんですね。で、その時に、まぁいろいろどうやって進めましょうかとか話をしてた時に、坂本さんのパートナーの方がですね、そういえば坂本さんが大手術を経験したその入院中にですね、「ぼくはあと何回満月を見るだろう」って、ふと呟いたというような話が出たんですね。はぁ……それはなんか、すごい心を打つなとか、胸打つなってみんな思ったんですね、その場に4〜5人の関係者がいて。で、そん時にもうタイトルが決まったな、っていうなんかちょっと職業病的な感じで言ってる感じがありますけれども、すごく素晴らしいタイトルだと思ったんですね。で、このタイトルは実は、坂本さんが兄……や父とも慕ったと言ってもいいかもしれないですが、ベルナルド・ベルトルッチっていう、あの監督で彼の為にもちろん映画音楽をたくさん作って、アカデミー賞にも映画音楽の賞を獲るんですけども、日本では公開されたのは翌年の91年ですが、発表された『シェルタリング・スカイ』っていう映画があるんですね。大変、まぁ深刻な映画で、いい映画なんですけども。で、それはあの、ポール・ボウルズっていう、アメリカの彼は音楽家でもあって作家でもあってって、いろいろな活動をしたポール・ボウルズっていう人が、1949年に出した「シェルタリング・スカイ」っていうのがありまして、それを元にしてシェルタリング・スカイというタイトルの映画になったんですね。で、シェルタリング・スカイは、あの、翻訳本が出てまして、日本語のタイトルは忘れたんですが、シェルターっていうのは、核シェルターっていうようなことで守ってくれる、覆いみたいなもんですね。で、スカイってていうのは、もちろん青空……昼間は青いんですけど、夜は暗くなりますけども……それでもって、人間とか生体にとって有害なガンマ線みたいなものとか、宇宙のいろいろな放射線等も含みますが……を、空が守っているわけですね。で、空の、その昼間明るい空の向こう側は、だから真の闇。で、もちろん空気もないわけですから、そこには音楽もない、つまり音がない、わけです、音楽もないんですけども。そのシェルタリング・スカイっていうタイトルだから、ちょっと意味深なんですね。「極地の空」ってのが、翻訳版だったかな。その「シェルタリング・スカイ」の中の、ポール・ボウルズの言葉に、原文では "We"って言ってますが、"私達(僕たち)は、何回満月を見るだろう"という言葉があるんです。で、ここに来るときにちょっとスマホでチェックして、その文脈が分かる箇所が、まぁ英語だったんですけども、それを抜き出してきたので、もうこの場での僕の訳だからちょっと変なとこあるかもしれませんが、それをちょっと引用してみたいと思います。"自分がいつ死ぬか、僕たちは知らない。なので、人生は汲めど尽きせぬ、井戸のようなものだ、と考えるに至っている。それでも経験できること、の数は限られている。それは極めて僅かな数でしかない。子供の頃のある午後の、そしてそれは今、の自分の人生がそれなしでは考えられなかったような、深い影響を与えた午後なのだけれど、でもそれを僕たちはあと何回思い起こすだろうか。4回、それとも5回、いやもっと少ないかもしれない。僕たちはあと何回、満月が昇るのを見るだろうか。20回だろうか。そしてそうであるにも関わらず、人生に限りがないように、思うのだ。"っていう一節があるんですね。で、20回だろうかって言ってた、それが、その僕たちあと何回、満月を見るだろうか。えっと、無限にもしかしたらずっと続くかもしれないと思われていた、自分の生がいつか終わるってことは分かってる、わけだけども、そこで最も重要な、あるいは最も影響を受けたようなそういう経験すら、あと何回ある大事なこと……それを仮に、満月というものに託して言うと、その僕たちを守ってくれているこの空に、満月が立ち昇るのを見ることがあと何回あるだろうかという、何かそういう感じのことなんですね。で、そのことを坂本さんはその、大病をされて入院されてる時に、ふと呟いたということ、だったんですね。それが、この連載のタイトルの由来……です。ということで、そのことをまぁご紹介したいと思いました。で、そういうこともありまして、なんていうんでしょうか、まぁ今回は、坂本さんの音楽史みたいなものを、振り返ってみたいなと思ったんですが、そこまではちょっとなかなか行ききらずに、この連載の、まぁタイトルの話に託してですね。今も音楽活動と、まぁいわゆる闘病と、非常にあの、積極的にお続けになっておられます、坂本さんは。」
「雑誌『新潮』で、私が聞き手を務めています、坂本さんの自伝の連載ですね、「ぼくはあと何回、満月を見るだろう」。こちらの最新版10月号、9月7日に発売になります。こちらもよろしければ、手に取っていただければと思います。」

<対談:鈴木正文×内田樹>
「今夜はゲストをお一人、あのお招きしておりまして、フランス文学者で武道家で思想家の内田樹さんです。内田さん、樹さんは、あの、まぁほぼ、坂本さんよりは若干年上、一歳か一学年上なのかな。えっと、まぁ色々積極的に、思想的な問題も含めてですが、あるいは民主主義的な、民主主義とは何かとか、まぁ選挙とか、最近話題のカルト教団のことなんかについても、ちょっとお話うかがってみたいなと思っています。」
鈴木「内田さん、どうぞよろしくお願いします。」
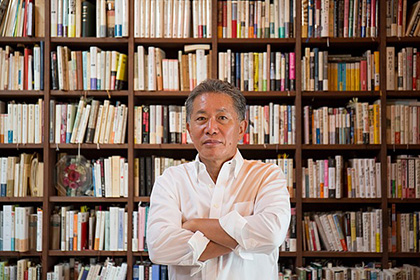 内田「よろしくお願いします。」
内田「よろしくお願いします。」
鈴木「こちらこそ。」
内田「お久しぶりです、本当にお久しぶりですね。2年ぶりぐらいですか。」
鈴木「いやー、そうですね。いまZoom越しで、そのお顔を拝見してて、全然お変わりないですね。お元気そうで。」
内田「そうですね。コロナでずっと、まぁいろんな活動は、ずいぶん自粛してましたけども。ここのところ割と、結構出歩いてるんですけどもね。」
鈴木「あ、そうですか。なんていうんですか、いわゆるリモートでは何回かね、お会いしてますけれども。それでまぁ久しぶりにですね。坂本さんの番組のお力をお借りて。」
内田「はじめ、坂本さんの番組って聞いたから、え、坂本龍一さんがラジオに呼ばれるのかなと思って、どうしてかなと思って。僕、お会いしたことあるんですよ、実は。」
鈴木「あ、そうですか。」
内田「えっとね2015年。安全保障関連法案に反対する学者の会ってやってた時に、坂本さん、音楽家の会っていうのを作られて、映画人の会とかいくつかその並行して会があって、その時に僕、その坂本さんと連帯してやりましょうということで、割と事務的なやりとりをしたことがありましたね。」
鈴木「あぁ、そうですか。」
内田「あと、大滝詠一さんのご葬儀の時に、お会いしてその時に自己紹介して。握手をしていただいたことがありました。」
鈴木「(笑) 大滝詠一さんはね、だって、内田さんもね、大ファンですよね。」
内田「そうです。ずいぶん親切にしていただいた、私の兄貴分でしたから。」
鈴木「まぁ、内田さんはだから、その二つ下っていうことですよね。」
内田「1950年生まれです。坂本龍一さんは、学年僕のが1個上なんですよね。」
鈴木「えぇ、で、僕が1949年ですね。」
鈴木「ちょっとまぁ、いつも、まず真っ先に今、ちょっとこれ、どういうことなのってお考えになってること、なんでしょうか。」
内田「いっぱいありますけどもね。それは、日本の政治はどうなっちゃうんだろうってことでしょうね。」
鈴木「非常にまずいですけども。まぁ、考えてみたらずーっとこの20年以上まずいのが続いてますが、まぁとりわけ何かもう原発再稼働だとかですね、何か増設するとか、新世代なんちゃらみたいな、ことをまぁ、突如として言い出して。」
内田「出てましたね。なんでこと言い出したのか、ちょっと分からないですけども。」
鈴木「まぁ、そんな中、ウクライナのせいなのか、みたいな話に。」
内田「今から作ったって間に合わないでしょ(笑)。当面の電力不足に間に合わせるのは無理だと思いますけどもね。」
鈴木「そうですね。」
内田「何なんでしょうね。なんか知らないけど。やること本当にちぐはぐで。何ていうのかな、ビジョンがないっていうか一貫性がないっていうか。何がしたいか全然わからないっていう感じで。」
鈴木「うん。そうですね。」
内田「何とかしてとにかく、あの今日のタスクを終わらせてっていう感じが精一杯で、政権維持のためだけに、何とか必死になってやってるけども、その点を繋いでいった後に、一体どこに行くのかっっていうのが、なんかもう……ひたすら没落の道しか見えないっていうね、感じですよね。だって、あの支持率が、いきなりどかーんと下がったわけでしょ。」
鈴木「はい。そうですね。」
内田「16ポイント下がったのかな。凄まじい下がり方ですよね。だって、これね、もうどう考えてみても、これ、原発再稼働なのかだからといって支持率が上がるわけないわけだから。」
鈴木「うん。」
内田「これからあと支持率が上がりそうな政策って何にもないわけで。ひたすらこれからあとですね、その支持率下がっていくだけだと思うんですけども。でも黄金の3年間とか言われているわけだから、その国政選挙はないかもしれない。そうすると本当にですね、全く支持率のない本当に2割台とか、場合によっては1割台……の政権がだらだらだらだら続くというですね、このご時世にですね、そういう支持率の低い政権でやっぱり大胆な政策っていうのは、何やろうとしてもね、国民の大半が反対するっていう感じだから、断行できないってことあるでしょうから、どうなるんでしょうね。」
鈴木「それにしても、その程度のことはだって、分かりますよね。まぁ彼本人も、それで支持率がばんと上がるとかね。本当に信じてるわけじゃない、ですよね。」
内田「比率が上がる手だって、もちろん官邸必死になって考えてると思うんですけども、何一つ思いつかないっていうので、とりあえず誰かが喜ぶっていうと原発再稼働っていうと、それはもちろん、あの財界とかですね、ゼネコンとかを大喜びするはずだから、誰かを喜ばせようと。多分国民は何やっても喜ばないので、しょうがないから、とりあえず確実に喜んでくれる人が、1人でも2人でもいる政策をやろうということで。まぁこれやると、とにかく原発再稼働に踏み切ると、喜ぶ人は結構多いですよね。国民のごく一部に過ぎないけど。」
鈴木「うんうん。まぁただ、その実際、例えば、今既に停止中の地域の住民たちについてはですね、必ずしも歓迎っていうふうなムードではないって、もう既に伝えられてますからね。」
内田「ないでしょ、それはだって。福島の事故があった後ですからね。あれからだってね、結局東電がやっぱり大きな責任があったっていう判決が出たばっかしじゃないですか。その大きな責任を抱えている電力会社に一体、今、今季、あれからあと、どれぐらいそのね、彼らがその心を入れ替えてですね、安全管理にすね、これまでとは全く違うようなレベルの安全管理の方にシフトしたのかっていうと、全くそんなこと感じられないわけですよね。」
鈴木「本当ですよね。」
内田「どんどんどんどん電力会社自体お金なくなってるわけだし、こんなところにコストを使うことができなくなってる状況でしょうからね。もっともっとレベルの低いね、老朽化した原発を動かすわけでしょ。」
鈴木「まったくそうですね。」
内田「そりゃ、その地元住民だってもう嫌ですよ。自分の故郷から永遠に出ていくとか、そもそも故郷が居住不能になるとかってリスクがあるわけですから。」
鈴木「まぁまるで、それはそれこそ戦争で避難民化するみたいなことに、まぁほとんど同じことを意味するわけですね。生活上の変化で言えば。」
内田「そうですよ。本当にそうです。本当に原発というか、安全環境なんていって、どう考えてみても、福島の時より劣化してるわけですよね。異常気象とかって起きてるわけで、例えば今ヨーロッパの方では原発止まってますけど次々と。あれ、大体原発って川のそばに作ってあるんですね、大量の水がいるから。」
鈴木「そうなんですよね。干上がっちゃうから。」
内田「ところが水が干上がっちゃって、その冷却水が利用できないから止めてるわけですよね。まさか異常気象で温暖化すると原発が止まるなんて誰も思ってなかったですね。」
鈴木「そうですね。」
内田「でも温暖化してみたら、川が干上がってしまって、あるいは内海のそばにある原発だったら、海が干上がっちゃうってあるわけですよね。」
鈴木「全くそうですよね。」
内田「誰も考えてなかっただろうし。実際に今、北朝鮮はミサイル飛ばしてるし、中国は台湾海峡で軍事的緊張高まってるわけであって、日本なんてその原発海岸沿いに並んでるわけですからね。原発にミサイル撃ち込まれたら、もうそれで日本も万歳じゃないですか。」
鈴木「本当そうですね。」
内田「だからそれ考えてみたらね、周りの地政学的環境とか異常気象とかを考えてみたら、今、原発再稼働なんて選択肢としてあり得ないと思うんですよね。」
鈴木「よく仰ってくださいました。」
内田「ありがとうございます(笑)。」
鈴木「私も100%、120%、当然のことながら同感なんですが。まぁ坂本龍一さんも、当然同じご見解だと思いますが。まあ、その発送電の分離うんぬんの議論は若干出ましたけれども、実際その再生可能エネルギーの可能性っていうのは、まぁ果てしなくあるはずなんですけれども、それを本格的に、その行政官の方で研究して、政治家、立候補で選ばれた政治家がですね、一緒になって、こう頭を捻ってるっていう、そういう報道はとにかく目にしたことないですよね。」
内田「そうですね。ほとんど捻ってないと思いますよ。既得権益を維持するっていうことで精一杯で。だからもう電力会社に飼われてるって言っていいんじゃないですか日本のエネルギー政策は。」
鈴木「まぁ、そういう電力を商品化する、まぁお金で売って、まぁお金で売るのは、例えばそれが国営企業で仮にやったとしても、一定程度の負担というのがあるのはもちろんでしょうが、先ほど内田さんおっしゃったように、なんていういうんですか、金儲けの手段にしていくっていう。」
内田「絶対そうですね。ライフラインはね、お金儲けの手段にしていけませんよ。」
鈴木「そうですね。それはあの、まぁカントが……っていきなりそのカントが(笑)」
内田「いきなりカントが。」
鈴木「出るのも変ですけども、人間を手段としてのみ扱ってはいけないという。目的としても扱え、というふうに、『永遠平和のために』ですとか……で、最後の本ですけども、言ってますけれども。もちろん、その目的として扱わなければいけないものを、手段として扱う……手段としてのみ扱うっていうのは、倫理的に正しくないっていうのはカントの考えですが、これは例えば空気とかね、水とかっていうのも同じで、土地もそうでしょうが、」
内田「そうですよね。」
鈴木「そのように考えるわけで、ましてやその、現代人の生活にとってもはや不可欠な最重要なインフラストラクチャーの一つになっている電力をですね、私企業の利益のために、株主の配当のために商品化していくっていう、この考え方そのものを根本的に疑っていくっていうね、そのことはやっぱ本当に問われてるんだろうと思うんですね。そうした中で、もちろん気候変動の問題があって、気候変動の問題に対処しつつ、その電力の供給と、まぁ享受の理想的なあり方っていうのを、どう考えていくかっていうことは、そんなに考えること自体は難しいことじゃないだろうと思うんですね。まぁ、いろんな考えがもう既に出されているわけで、それをどう実行するかっていうことは、行政府が立法に当たっている議員たちと一緒になってですね、本当に真剣に考えていただきたいと、まぁ思いますよね。」
内田「どれぐらい自由な議論ができるんですかね。僕なんか、政治家と話してて、エネルギー戦略の話になると、みんな突然顔が強張ってしまってですね、その話は、してもしょうがないんだっていう感じになってですね。」
鈴木「うん。」
内田「その日本の場合って、とにかくその原発、僕はずっと原発反対って若い頃から、原発反対のバッチとか付けてて、」
鈴木「同じです(笑)。」
内田「横にいたおじさんに絡まれてですね、てめぇ、原始時代に戻ってもいいのか!みたいな感じのね言われたことがあるんですけどもね(笑)。昔、僕は原発反対ですけどもって言った時に、当時の民主党ですよね……国会議員たちと、その時なんかそのセミナーか何かやってる時に、色をなして怒鳴られたことありますよね。」
鈴木「なんですかね。」
内田「95%のですね、海外からエネルギーに輸入してる国はですね、自前でできるって言ったら原発しかないんだ!って言いますからね。」
鈴木「だってウランは輸入してますからね(笑)、自前じゃ出来ないですよね。」
内田「ね、本当に(笑)。それは安全保障上の問題として、とにかく原発が一番有利なんだっていうことを言って、その目が三角になって怖くてですね、議論とかできないんですよ、なんかね。」
鈴木「まぁ、そこで何か僕は大して取材もそれはしてないんですが、やっぱりナショナリズムというんでしょうか……まぁいわゆる大国ナショナリズムみたいなもんで、その核武装をすべしとかね、いずれそういうことを遠望している政治家っていうのはいますね。例えば、戦前のようにまぁ列強に越していくっていう。」
内田「石破さんなんか、はっきりそう言ってませんでしたっけ。やっぱし自民党としては、核武装のための基礎的なテクノロジーってのは手放したくないんだっていうね。」
鈴木「そうですね。いつかアメリカにから、いま従属していると、隷属していると、いうふうに僕たちは批判されてるかもしれないけれども、心の底では自立するんですよっていうね……まぁ、軍事的な自立を含めて。」
内田「それはどこまで思ってるかなあ。安倍晋三は思ったと思うんですよね。あのどこかでアメリカに一矢報いたいっていうのがあって、そのアメリカに対する屈折した怨念みたいなものに共感する人たちが、あのネトウヨ層の中でもかなりいたと思うんですけども。果たしてですね、今の政治家の中に、アメリカの寝首を掻きたいなんてことを、本当に思ってる人ってね……いるのかなあ。」
鈴木「まぁ、いないと思いますけれども。まぁ、いずれにしても、例えばその共同防衛であるとか何とか、で、その核テクノロジー、まぁそれを武器化するとかですね。そういうことに1枚噛んでいくっていうことが、ナショナル・インタレストであるっていうような考えが、どっかに残ってる……可能性あるんじゃないかなと思いますね。」
内田「それはとにかく絶対口に出して言えないってことですよね。口に出して言った瞬間にやっぱし、日本の場合、まだ属国ですからアメリカのね。アメリカの世界戦略に対して、独自の世界戦略を持つんだ核武装して、なんてこと言ったら、基本的にはその政治家は、とか官僚でももう終わりですからね。それはね。」
鈴木「ということで、何かあの、非常にモヤモヤとした……」
内田「(笑) そうなんです。」
鈴木「(笑) エネルギー問題の本当の核のあたりに、まぁここまで、例えば地震の国であるとかですね、津波もあるでしょう。それから、その非常に脆弱な防御体制しかない、とかですね。それから当然のことながら、もんじゅの失敗であったりとかですね。それから核廃棄物の自前での処理ができないとか。どうにもならなくて、さすがに小泉純一郎をしてですね、原子力発電はやめるべきだというふうなね、ことを言わせしめるほどの状況にありながら、なおかつこの時点でですね、夏の電力不足が理由になってる、っていうふうな理由もありますけれども。まぁ何十年後かの……」
内田「これはもう完全に私企業の個別の利害に尽きると思いますよ。そこからやっぱしね、お金が、大量のお金が、献金があるわけだから、その人たち喜ばせるために国民の過半がそれに対して反対しても……もう国民の過半が反対してもいいや!ってね。どうせ何やっても反対するんだろうからっていう、ことなんじゃないですかね、ここまでその統一教会問題が出てきてしまっては。」
鈴木「全く。実にこう何て言うんすか、僕たちの視界がぱっと開けて、気持ちが明るくなるような……そういう話題がないんですけども(笑)。」
内田「いや僕ね(笑)、あの意外に、ここまで支持率下がってしまって、あとはね、あの統一教会の関係者を大量登用しないと内閣も組閣できないっていう状態になってしまってですね。まあね、あの首相自身がかなり統一教会と深くコミットしていることがニュースが出てきているので、これここまでいっちゃうとね、突き抜けてしまったっていうかですね。公党としての、何かもう基本的な倫理的なギリギリのですね、建前みたいなものっていうのが、ほぼ崩壊しちゃったっていう感じがあって。僕、定期的にタイのバンコクの中高生たち、小学生、中学生、高校生たち相手に授業をやってるんですけども、昨日授業やってたんですよね、ちょうど昨日の午後授業やったんですけども。昨日のテーマは「民主主義」というテーマで、民主主義についてみんなどう思いますかっていうですね、話を90分したんですけどもね。みんなからその最初に、民主主義ってうまく機能してると思いますか。で、もし民主が機能しなくなるとどんなことが起きると思いますか。ってなことをアンケートを取ったら、15人ぐらいの子供たちから回答が来たんですけど、ほぼ全員がですね、民主主義の最悪の形態が衆愚政治だっていうふうに(笑)。」
鈴木「あー、なるほどね。」
内田「多数の専横と衆愚政治っていうんで。特にその多数の専横という、多数派が少数派の声を聞かないでですね、もう自分たちのやりたいことをやっていくっていうですね、多数の独裁ってことについては、多分学校でも習ってると思うんだけども。あの、学校の教科書ではね、衆愚政治って言葉は教えないと思うんですよね、毒が強すぎるから。」
鈴木「ええ。でもその言葉が出てきた。」
内田「(笑) でも子供たちが今、一番不安に思ってるのってのは、知名度が高いだけで、まったくそのね、頭の空っぽの人たちっていうのが、どんどんどんどん国会議員になっていくっていう。これ、危険じゃないでしょうかっていうこと。だから、子供たち見てるわけですよね。現代日本の政治をですね、子供たちが最も危険な兆候としてですね、衆愚であると。つまり国会議員の知性特性において、一般の国民よりも良質とは言えない、選良ではないと。むしろ、一般国民の知性特性よりも低いかもしれない……そこまで、国会議員に対しての評価が下がってるっていうのを、コメントを読んでですね、目の当たりにして、かなりショック受けたんです。」
鈴木「それでその、あの一時、なんか小選挙区制ってやったじゃないすか。まぁ衆議院の選挙で、日本が。それは政権交代が起きるようにっていうことで、まぁそういうことをやって。実際一時、民主党政権が例えば誕生すると。それは小選挙区制の力もまぁあったんじゃないかとも思えないこともないんですが、いわゆる二大政党制……なんていうんですか、コンプレックスって言うんでしょうか、戦後日本がね。何かそういうものを政治家だけか、あるいはジャーナリズムを持ったかどうかわかりませんが、何かそういうものがあったように思いますね。で、中選挙区制がなくなって、まぁ勝者総取りっていうんでしょうか、ある種の。民主主義が仮に、まぁ仮にじゃなくて本当は多様な声を反映するシステムとして考えられているのだとしたら、間接議会制民主主義ですから、議場にですね、民意がより多く反映されるためには、やっぱり小選挙区制っていう、その選挙制度そのものにもこの辺でっていうか、もう遅きに失しているかもしれませんがメスを入れるべきじゃないかって僕は思ってますが、内田さんなんかその辺のことについて、どんなふうにお考えでしょうか?」
内田「まあ、全く同じ意見なんですけどね。小選挙区制で、ずっと選挙圧勝してるわけですから、自民党がですね。だから自分たちが圧勝してるような。」
鈴木「そうですね。変える理由がないんですね(笑)。」
内田「わずかな支持者さえ、コアな支持者を固めていれば、あととにかく危険率さえ上げておけばですね、永遠に政権が維持できるわけですから、これはあの、自分たちで変えるっていうような動機は、その利害関係から考えてゼロですよね。」
鈴木「なるほど(笑)。」
内田「あとそれからあの、なんつったらいいんだろうな……あの少数の人間がレバレッジを使ってですね、実際には国民の一部しかいないんだけども、それがこういう何つうのかな、小選挙区制みたいなレバレッジを利用していって、一気にですね、その実際には比例だと17%ぐらいしか取ってない自民党が国会議員の専有率6割超えるような議会を取ってしまうっていうので、これって株式会社の経営とか考えると、まぁおかしくないことなんですよね。」
鈴木「あぁ、なるほど。確かに。」
内田「その、少数の人間がレバレッジを使ってですね、いきなり大きな影響力を発揮するっていうのって、これ複雑系って基本そうなんですよね。少数のわずかな入力変化によって、劇的な出力変化が生じるっていうのって複雑系の基本だけど、政治ってまさに複雑系なんですよね。」
鈴木「なるほど。」
内田「だから複雑系だと考えると、まあ昔カナダでありましたけども、その小選挙区制でですね、与党が198議席から2議席まで落ちたということがあるんですよね、なんか(笑)。あり得ないような劇的な敗戦とか、劇的な勝利がありうるわけであって。こういうのってビジネスマンからしてみると、あのすごく、何ていうのかな、性に合ってるっていうかですね。例えばその、昔あったじゃないですか。例えばその、えっと、ベータとVHSの競争みたいな感じですよね。」
鈴木「はい。そうですね。」
内田「あれ51対49ぐらいのマーケットシェアの時に、あっという間に51が100になるわけですよね。こういうのって、多分ビジネスマンからしてみると、そういうもんでしょって。そのずっとマーケットがVHS59のベータ49ので推移していくよりも、VHS 100になった方が、そのね、機能がどうこうって問題じゃないんだと。それはビジネスって、そういうもんだから。」
鈴木「なるほど。ソリューションの効率が高くなるっていうことですよね。」
内田「なんか知らないですけど、ビジネスでそういうもんだからっていうのは、本当にね、今の政治家たちの中になんかそれ入ってて、今おっしゃったみたいにですね、多様な民意を、いろんな民意を、その全部それに応分した数だけの代表者を国会に送り込んでいって、あの国議を議していくっていうのは、そんな……能率の悪いことなんて俺らしてねよっていうね。普段してねぇからっていうね。こんな言葉遣いはしないでしょうけども(笑)。」
鈴木「してるんじゃないんですか(笑)」
内田「そんなことをやってもの決めてる組織が日本国内にあるのかよっていうね。」
鈴木「会社がありました、ということですね。」
内田「まさに、会社は違うだろってことです。会社でトップに全権集中していてね、トップが全部決めていいわけですよね。自分のアジェンダに賛成する人間登用して、反対する人間は左遷して構わないわけで。」
鈴木「安倍さんは行政府の長だって言ってましたからね。」
内田「いや、立法府の長って言ったんですよ。でも、政府の長なんですよね(笑)、内閣総理大臣は。」
鈴木「ごめんなさい、立法府の長って言ってましたからね。」
内田「ああいうのは、言い間違いとは言わないんですよ、4回も間違えたんだから。」
鈴木「そうですね(笑)、それみたいなもんですね。」
内田「会社のね、自分は経営者だと思ってるわけだから、自分の経営判断が間違ってるか正しいかってことは、どうやって決めるかっていうと、普通はマーケットが決めるわけですよね。」
鈴木「そうですね。」
内田「そのマーケットで売り上げが伸びるとか、収益上がるとか、株価が上がるか、ということで。」
鈴木「それが選挙ですね。」
内田「あの人たちはそう、選挙なんですよね。そのマーケットが、本来、日本のマーケットってのは、国際社会であるべきであって、国際社会におけるその国のポジションというか国力ですよね。国力のランキングを、外交力であったり経済力であったり、文化的な発信力であったり。地政学的なプレゼンスであったり、そういうものによって国力を図るべきなんだ。それは一切見ないと。とにかく選挙の国内における、ドメスティックな選挙結果だけを見て、マーケットって言ってるわけですよ。これ、いつも言ってることですけども、日本の政治って、株式会社みたいな経営するって言ってるけども、社内の人気投票で経営者を選んでる……社外のマーケットの評価ってのは、一切見ないっていうんですね。そんな株式会社ないだろうと思うんだけども、それを本人たちは株式会社のつもりで、それが世界の世界標準だからっていうつもりで、多分やってる……んじゃないかな。」
鈴木「非常に説得力のある議論ですね(笑)。どうしたらいいでしょう、ねえ。本当に手に負えないですね。まぁその子供たちが、その衆愚政治であるっていうね、その、民主主義がこのままでは、自分たちの将来にとって必ずしもいい……彼らがね、今、目の当たりにしてるものでは駄目なんじゃないかって考えているっていうのは一つの希望ですけれども、実際のところが、まぁ大人サイドとしても、これをどうにか改革していく必要が当然あるわけですが、まずどこから手をつけていったらいいでしょうか。」
内田「ね、その制度の問題として民主主義って結局何だかんだ言いながら、最終的に人類が到達した統治形態としては、まぁ相対的にはこれが一番ましなわけですよね。」
鈴木「チャーチルが言ってましたね。」
内田「チャーチルがね。その最悪のね、The Worst Form of Governmentなんだけども。これまでの全ての統治形態はもっと悪いって言ってましたけども。」
鈴木「そうですね。」
内田「あの、それ何でかっていうと、民主主義ってやっぱり制度としては非常に不出来なんだけども。なぜかっていうと、いま言ったみたいに簡単に衆愚政治に堕すわけですよね。簡単に衆愚政治に堕すってことは、あの、結局、民主主義が生きるかいけないかっていうのは、構成員の成熟度にかかってることなんですよね。」
鈴木「おっしゃる通りですね、なるほど。」
内田「制度の問題じゃなくって、国民国家の成員たちがどれぐらい愚慤……賢愚に懸かってるっていうね。賢いのが居るかっていうですね。言ってしまうともう、愚者が増えてしまうという衆愚政治になると。賢者が増えれば衆賢政治になると、賢人政治ですよね(笑)、プラトンの哲人政治に類したものになってるわけで。制度として非常に不出来ではあるけれども、でも、その個人的な努力の集積によって、民主主義社会の成員が1人ずつ大人になっていくと、それで変わるっていうですね。あの制度をいじることはできないけれども、人間の個人的な努力の集団的な集積によって、制度が健全に機能することはありうるという、そういう何ていうのかな……すごく開放的な制度だって気がするんですよね。」
鈴木「なるほど。ていうことは、みんながちゃんと、えっと、なんていうんですか(笑)。」
内田「ちゃんとすればいい(笑)。そのどこが解決策だって言われそうだけど(笑)、小学校の児童会じゃないんだぞ、馬鹿野郎って(笑)」
鈴木「ちゃんとしてるよーみたいな(笑)。」
内田「でもね、みんながちゃんとすればいいしかないんですよ、本当にこれ、いろいろ考えた結果ね。何十年間いろいろ考えた結果。みんなでちゃんとした方がいいと思います、はい!っていうね(笑)。」
鈴木「本当ですね。50年前も同じこと言ってたような気がするんですけど。」
内田「(笑) なんか、いや若い頃はね、何か制度を変えなきゃいけないっていうね。人間は変えられないから、制度を変えようって言ったんですよ、やっぱし。」
鈴木「あぁ、そうかそうか。」
内田「人間の本質って変わらないから、もう歴史的な条件を変えていくしかないんだってですね。外から変えていくっていうふうに考えてたけど。長く生きてきて、外からいくらいじっても駄目っていうのが分かって、中身が同じだったら駄目っていう(笑)、中身変えなきゃって。」
鈴木「それは確かに、そうですね。まぁボリシェヴィキ革命からスターリン主義へっていうね、まぁ、そういう経緯を見てみると、あれは一種の強行的な制度改革をいきなりやったわけですよね。でもやっぱり人間が変わってないと。」
内田「あれー、うん。そうです。あれスターリンじゃなくて、もうちょっとまともな人たちがですね、まともな人がレーニンの次に出てきていたら、ねえ。」
鈴木「どうなってたんでしょうかっていうね。」
内田「まぁそれはマルクス主義……ロシア・マルクス主義というものが、どうなったかって全然わからないですよね。」
鈴木「そうですね。」
内田「非常に属人的なものなんですよね、あのシステムって怖いのは。」
鈴木「うんうん。本当にそうですね。」
内田「マルクス主義……怖いのは非常にその属人的なその条件によって劇的に変わってしまうので。」
鈴木「側面があると…。」
内田「そうです。まぁ、賢者がトップにいれば機能するけども。やっぱ帝政とか君主制と、あんまり変わらないんですよね、あの仕組みってね。それに比べると、衆愚政治の方がまだしも……(笑)、スターリン主義よりはまだしも。」
鈴木「そういえばこの番組にも、坂本さんのゲストとして、斎藤幸平さんがお出ましになったことがあるようなんですけれども、内田さん最近対談されたというようなことを誰かから聞きました。」
内田「最近でもないですけど、凱風館においでいただいて、そうですね。お話聞きました。」
鈴木「内田さんはあの、マルクス主義者というわけではないんですけれども(笑)。」
内田「まあ、あの僕は、マルクシアン。」
鈴木「マルクシアンですね。」
内田「マルクシストじゃなくて、マルクシアンです。」
鈴木「新旧……まぁ年齢差がどれぐらいあるんですか。」
内田「40歳ぐらいあるのかな。彼まだ30代はじめくらいでしょうかね。」
鈴木「どうでした、新しい時代のマルクシアンに。」
内田「いやー、やっぱし、マルクスを語るときの言葉遣いが、全然違う。視点も違うし。どんな場合でもそうですけども、物事を根源的に考えるっていうときに結局、その僕らみたいな文化研究でも何でもそうですけど、結局元のテキストに戻っていって、そもそも本当は何を書いていたのかっていうですね、その草稿研究まで戻っていくっていうところがあって。そこを戻っていくと、これまで全然誰もマルクスがそんなこと書いたって知らなかったことが出てくるわけですよね。斎藤さんがそこから始めていって、で、マルクスの中にあるですね、その社会関係だけ見てたわけじゃなくて、もっと長いスパンですね……ある地質学的な時間の流れの中での人類の運命ってのを考えたんじゃないかっていうことに注目していて。」
鈴木「なるほど。」
内田「これはね、『資本論』読んで、マルクスが地質学的な時間の流れの中で、人類の衰亡を考えていたっていうところに気がつくって人はね、なかなかいないと思うんですよ。あの資本論の中に有名な大洪水ね、"大洪水よ、わが亡きあとに来たれ!"ってありますけども、わりとキーワードなんですけど。あの大洪水っていうのは、普通は大きな社会的な変化を考えて、その資本主義……恐慌であったり、あるいはそのプロレタリア革命であったりっていうふうに、どうしてもすごく小さく考えちゃうんだけども、あの斎藤さんはあの大洪水ってのを本当にその異常気象であったりですね、本当に人類が破滅するような、そういう形っていうふうに考えてすると、マルクスがどこまでその本気で大洪水のことをイメージしたのかっていう……これね、僕、近年マルクスについて聞いた中で最も刺激的なアイディアで。」
鈴木「うん。」
内田「いま僕はずっと、石川康宏さんと一緒に、「若者よ、マルクスを読もう」というシリーズを、もうかれこれ10年以上続けてて、ついに『資本論』に到達して、これでおしまいなんですけども。やっぱりその資本論を読むときに、やっぱりすごく、あの斎藤さんの影響を受けましたね。」
鈴木「あぁ、そうですか。僕たちの頃ってやっぱ価値論がほぼ主要な、なんですが資本論の読みどころとしては……まぁ、僕なんかもっぱら価値論を、それから資本の原始的蓄積。」
内田「資本論て読むと、最初、これが資本論かよと思ってね、みんなやめちゃうわけですけども。やっぱりね、あれ終わりの方の資本の原始的蓄積っていうところからあたりが、すごく面白いわけですね。やっぱり若い人たちにですね、資本論もう1回読み直してください。と、いうことを、中高生相手に書いてるということなんですね。いま一生懸命、大洪水論を書いてるとこなんですね。」
鈴木「あ、そうですか。それはでも、本当にみんながちゃんとするっていう……まぁさっきの話に戻りますと、そのためにも(笑)。」
内田「(笑) まず中高生から、もう大人に言ってもあんまりしょうがないからね。これから、これから大きく伸びていく中高生相手にですね、マルクスはこう言ってるんだよ、まぁ、こっちいらっしゃい。ちょっとおじさんがお話聞かせてあげるからって言って。昔々マルクスという人がいてねっていう(笑)」
鈴木「まぁ、本当にえっと、まぁ根源的な、僕たちが今、差し向かい合ってるっていうんでしょうか。その根源的なその何か問題……まぁこれは他の誰でもない人間の問題であるわけなんで、それを改めて原点……なんていうんですが、そのことのそもそもの始まりに立ち返って考えていくっていうのを、ちゃんと……みんながちゃんとすることの第一歩として、いきたいという甚だ曖昧模糊とした、なんていうんでしょうか、結論にはならない結論かもしれません(笑)。ということで、今日はちょっと皆さんと一緒に考えていただくということで。」
内田「すみません。ベラベラ喋っちゃって。」
鈴木「いえ、またお目にかかりたいと思います。」
内田「またぜひ、今度は対面で、いっしょに。美味しいものでも。」
鈴木「はい、そうしたいと思います。どうも本当にありがとうございました。
内田「お元気で。あ、坂本さんによろしくお伝えください。」

|
■ 対談のノーカット版をYouTubeで公開しました。

|
|
|

<デモテープオーディション – U-zhaan, 長嶋りかこ, 蓮沼執太>
U-zhaan「J-WAVE レディオ・サカモト。ここからは僕、U-zhaanと、」
長嶋「長嶋りかこと、」
蓮沼「そして、蓮沼執太の3人でお届けしていきます。」
U-zhaan「今回も、いつも通り全員リモートでの審査となります。」
蓮沼「お願いしまーす。」
U-zhaan「リモートでの審査が続いてるのはやっぱり、新型コロナウイルスの影響だと思うんですけど、この2ヶ月の間に僕ら3人とも感染しましたよね。」
長嶋「しましたね。」
U-zhaan「うん。結構、同時期でしたよね。」
長嶋「そうですね。」
U-zhaan「僕の先月頭にあったイベントに、執太も長嶋さんも来てくれることになってたんですけど、2人とも来れなくなっちゃって。」
長嶋「あ、その時だったんだ、蓮沼くんは。」
U-zhaan「そうそう、うん。」
長嶋「そうなんだ。」
U-zhaan「その時、本当はトークショーの相手役をしてくれるはずだったんですけど。蓮沼さん来れなくなって。で、みんなかかっちゃったなぁと思ったら、僕もその翌日ぐらいにかかっちゃって。」
長嶋「あー、そっかそっか。」
U-zhaan「大変な世の中になってますから。」
長嶋「ね、多いですよね、今。」

U-zhaan「というわけで、今日も(優秀作を) 9曲選びました。長嶋さんは、あのストーブのやつが一番好きっていうことですよね。」
長嶋「そうですね、はーい。すごい好きでした。(「Midwinter Parafin Heater and Enka Cassette」Thomas Martin Nuttさんの作品)」
長嶋「U-zhaanは。」
U-zhaan「うん。僕は逆にDreams Comes True (noobtasticさんの作品) が、やっぱり……やっぱいいなと思いますね。」
蓮沼「(笑)いや、どちらも良かったよね。」
U-zhaan「うん。」
蓮沼「やっぱりその2曲は。」
U-zhaan「そうですね。」
長嶋「良かったよ。蓮沼くんは?」
蓮沼「僕はそうだな…。midunoさんのフィールドレコーディングが、今回はハマりましたかね。」
U-zhaan「はい。あの水中録音って、執太もマイク持っててやってるじゃない。」
蓮沼「やってますよ、はい。」
U-zhaan「あれってステレオで録ることもできるのかな。」
蓮沼「もちろん。」
U-zhaan「あ、そうなんだ。midunoさん作品がモノラルだったよね、今回。」
蓮沼「そう。あの、高さ変えたりとか。左を上の方にして、右を下……もっと深く、深いところにとか、いろんな位相を作って、単純に右と左だけじゃなくて、とか、もうちょっと複数で録るっていうときもあるし。」
U-zhaan「うんうん。」
蓮沼「いや面白いですよ。そういう。まぁ、あの流れが激しいと、マイクも動いちゃうから。」
U-zhaan「流れていっちゃう。」
蓮沼「流れちゃって。まぁでも、流れても、そのたまに岩と……岩とマイクがぶつかる音とかも、なんか良かったりとかして。」
U-zhaan「うんうん。」
長嶋「うん。」
蓮沼「いろんな、僕はどちらかというと、遊び感覚でやってる時が多いんですけど、水の音を録る時とかは。うん、面白いですよ。」
U-zhaan「なるほど。」
音楽ジャンルのオーディションが、音楽配信代行サービス「BIG UP!」と連携しました。

■音楽作品
「BIG UP!」のアカウントからエントリーをお願いします(「BIG UP!」での配信を希望される場合、そちらの登録も必要です)。
審査通過者には、副賞として「BIG UP!」のベーシックプランでの配信利用料が無料になるクーポンを贈呈いたします。



■音楽以外の作品
今まで通りノンジャンルで受け付けています。作品はファイルのアップロードのほか、YouTubeのURLを指定しての投稿も受け付けます。
詳しくは、エントリーフォーム内の応募要項をお読みください。

 |
|

|
番組サイト内エントリーフォームより御応募頂いた作品にまつわる個人情報の管理、作品の管理は、J-WAVEのプライバシー・ポリシーに準じております。詳細は、こちらを御確認ください。 |
|

U-zhaan「蓮沼さんは前回からの間に新曲を発表してますね。」
蓮沼「まぁ、えっと僕というか、蓮沼執太フィルっていうアンサンブルの新曲が、はい、リリースされました。」
U-zhaan「えー、J-WAVEの「INNOVATION WORLD」っていう番組とコラボレーションしてるってことなんですけど、どんなコラボレーションしてるんですか。」
蓮沼「実質的なコラボレーションではないんですけど、それこそ2年前かな……2年前の夏に初めてのコロナの感染が広がる時期があって、みんな家から出れない、まぁ出ないでくださいっていう期間あったじゃないですか。」
U-zhaan「はい。」
長嶋「うん。」
蓮沼「で、そのときにそのJ-WAVEのその「INNOVATION WORLD」の番組の企画で、何か生活の音を録っていただいて送ってください。っていうコラボレーションしたんですよね、募集で。」
U-zhaan「はい。」
長嶋「うん。」
蓮沼「で、それで集まった音で作ったのが、フィルの「呼応|Co-Oh」まぁなんていうのかな、ドラフトバージョンというか、下書きバージョンっていうのが出来上がって。それを出来上がってから、何度かライブする機会がまた増えて、コロナもちょっと落ち着いた時期とかもあったので。で、どんどんと曲が完成していって、やっと「呼応|Co-Oh」ていう形になってリリースしたという経緯がありますね。ちょっと複雑なんですけれど。なので、何か直接的なコラボレーションというか、最初に一緒に、この曲の何ていうのかな……原型を一緒に作って、発展していったという形です。」
長嶋「このジャケットもいいですね、これ「呼応|Co-Oh」の。」
蓮沼「そう、ジャケットはあの、オードリーさんっていうフランスのアーティストと平山昌尚さんっていう。」
長嶋「へえー。」
蓮沼「僕らひまさんって呼んでるんですけど。ひまさんとのコラボレーションで、これコロナだったから、コラボレーションなんだけど、郵便でお互いの絵にまた絵を描いていってっていうふうに。会わずして作っていったコラボレーションで、まぁ、それもなんか「呼応」しているっていうのは。」
長嶋「なるほどー。うんうん。おもしろい。」
蓮沼「っていうニュアンスもいいなあと思って使わせていただきました。」
長嶋「うん。」
U-zhaan「うん。デジタルじゃなくて郵便で描き足していくっていうのは、すごいですね。」
蓮沼「そうそうそう。」
長嶋「うん。いいですね。」
蓮沼「そのシュルレアリスム的な、そういう遊びがあったらしくて昔。そういう技法っていうのかな。それを現代版でやってみようっていうことらしいです、はい。」
U-zhaan「長嶋さんは、最近何してますか。」
長嶋「最近ですか。あの結構、本を今いくつか手伝いをしてて。スキーマ建築さんが、10月に尾道で、オランダの「LLove」っていう……ロイドホテルっていうホテルがあるんですけど、そのなんか、日本ってもう、アーティスト・イン・レジデンスみたいなことができるような施設を、LLoveさんとコラボしてスキーマ建築さんが主体で作るっていうことがあって。で10月にオープンなんですけど、そこに合わせて今、本を作るっていうのは、ちょっと手伝ってたりとか。」
U-zhaan「へえ。」
長嶋「うん。あと、丸亀で猪熊弦一郎美術館で、アーティストの今井俊介さんっているんですけど、その方が今展覧会やっているので、そのカタログの手伝いとか。今、下ごしらえ時期って感じです。粛々とやってます。はい。」
U-zhaan「へえ、いいですね。10月、僕尾道ライブ行くから。」
長嶋「え、マジで!?いつ。」
U-zhaan「うん。見に行けたらいいな、と。えーと、前半なんですけどね。オープンいつなんですか。」
長嶋「えーとね、確か10月頭……あ、1日。」
U-zhaan「1日、じゃあ行けるかもしれないっすね。」
長嶋「あ、本当!いつ。」
U-zhaan「10月の……」
蓮沼「あとでいんじゃね (笑)」
一同「(笑)」
U-zhaan「確かに(笑)。」
長嶋「今詰めようとしてた(笑)。」


<坂本龍一:プレイリスト「RadiSaka2022-09」>
今回も番組のために教授が選曲したプレイリストを25分間ノンストップでオンエアしました。Spotifyに、プレイリスト「RadiSaka2022-09」としてもアップしています。

|



 「ちょっと代読させていただきます。「スーさんとは」って、スーさんってすいません、あの、僕のことなんですね。鈴木なんで。あの、坂本さんいつも僕のことスーさんって、呼んでくださっています。「スーさんとは『音楽は自由にする』を作るときに」、この音楽は自由にするっていうのは、えっと2009年に新潮社から出版された、坂本さんの自伝本です。で、その時、僕は編集を担当したひとりでした。ということで、もう1回あたまから読み直しますと……「スーさんとは『音楽は自由にする』を作るときに、話し相手になってもらい、とてもお世話になりました。」いいえ、とんでもございません。「元々、スーさんと話すのが楽しく話がはずむので、今回の『新潮』の連載でも、スーさん以外の話し相手は考えられませんでした。」この今回の新潮の連載についてはあとでお話いたします。「なぜスーさんと話すのが楽しいのか。一つは世代が近いので、60年代の昔のこともツーカーで話が通じます。」確かに。「そしてスーさんはとても頭がいいので」いいえ、そんなことはありません。「どんな話題にも的確に、時にはこちらがとてもインスパイアされるような反応が返ってきます。」これは買い被り……だと思います。「そして二人とも考え方がリベラル、またグローバルなので、世界の見方も近いところがあります。」だといいんですが。「というような理由で」って、いちいちなんかツッコミ入れててすいませんね(笑)。「スーさんと話しているととても楽しいのです。」ありがとうございます。「今回は僕の代わりに番組を担当してくれることになりました。どうかよろしくお願いします。」もうとんでもないです。坂本さんの代わりは、とても務まらないんで、えっとちょっと今、暗澹たる気持ちが若干なんか胸の辺りを走りましたが。えーというようなメッセージをいただいております。で、またこの番組にお帰りになることは確実なことだと思いますので、ぜひその間、このレディオ・サカモトを含め、注目していただきたいと思います。」
「ちょっと代読させていただきます。「スーさんとは」って、スーさんってすいません、あの、僕のことなんですね。鈴木なんで。あの、坂本さんいつも僕のことスーさんって、呼んでくださっています。「スーさんとは『音楽は自由にする』を作るときに」、この音楽は自由にするっていうのは、えっと2009年に新潮社から出版された、坂本さんの自伝本です。で、その時、僕は編集を担当したひとりでした。ということで、もう1回あたまから読み直しますと……「スーさんとは『音楽は自由にする』を作るときに、話し相手になってもらい、とてもお世話になりました。」いいえ、とんでもございません。「元々、スーさんと話すのが楽しく話がはずむので、今回の『新潮』の連載でも、スーさん以外の話し相手は考えられませんでした。」この今回の新潮の連載についてはあとでお話いたします。「なぜスーさんと話すのが楽しいのか。一つは世代が近いので、60年代の昔のこともツーカーで話が通じます。」確かに。「そしてスーさんはとても頭がいいので」いいえ、そんなことはありません。「どんな話題にも的確に、時にはこちらがとてもインスパイアされるような反応が返ってきます。」これは買い被り……だと思います。「そして二人とも考え方がリベラル、またグローバルなので、世界の見方も近いところがあります。」だといいんですが。「というような理由で」って、いちいちなんかツッコミ入れててすいませんね(笑)。「スーさんと話しているととても楽しいのです。」ありがとうございます。「今回は僕の代わりに番組を担当してくれることになりました。どうかよろしくお願いします。」もうとんでもないです。坂本さんの代わりは、とても務まらないんで、えっとちょっと今、暗澹たる気持ちが若干なんか胸の辺りを走りましたが。えーというようなメッセージをいただいております。で、またこの番組にお帰りになることは確実なことだと思いますので、ぜひその間、このレディオ・サカモトを含め、注目していただきたいと思います。」
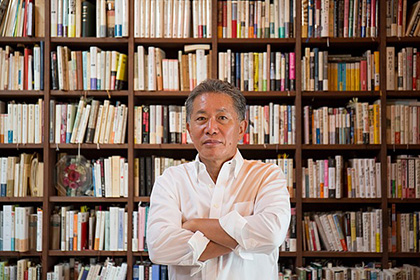 内田「よろしくお願いします。」
内田「よろしくお願いします。」