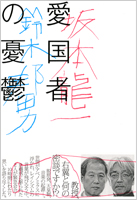「こんばんは、坂本龍一です。お正月も終わって、明日からはもう学校や会社が始まりますよね。2013年は、あっという間に過ぎてしまったんですけども、今年もそうなってしまうのでしょうか。なるべくあっという間に過ぎ去らないようにですね、何か一日一日こうじっくりと味わい深く生きていきたいと(笑)、いつも思っているんですけどね。もっと強く思うようにしようかな。」
「今年はですね、個人的にはソロ・アルバムの制作に集中しようかなと思っているのですよ。で、なるべく他の仕事は入れないようにしているんですけども、えー、7月から9月にかけて、札幌国際芸術祭というのが開催されて、それのゲストディレクターに指名されてしまったのでですね、それはきちんと勿論やりますけどもね。ですから、ソロ・アルバムの制作と札幌国際芸術祭とJ-WAVEのレディオ・サカモト、これくらいですかね。やるのは。そんなことないか(笑)、もう少しあるか(笑)。2月にあの、2013年も行ったんですけどソナーという音楽フェスでアイスランドに行ったりはするんですけど、なるべくそういう仕事は入れないようにして、もう、5年経ってしまっていますからね『out of noise』からね。」
<新春放談 2014>
「さて、今年最初のレディオ・サカモトはですね、『新春放談』と言いますかね、この何年か続いてますよね。別に新春じゃなくてもいいんですけど、いつ話しても大丈夫なんですけど、なぜか新春にこう、がつっとね、えー、話をしたいという感じ。年明けにものすごい濃い3人と話をして(笑)、濃かったですね、ほんとに。それぞれやはり面白かったし、この年の始めに、年を占うではないですけども、意味のある話がね、それぞれとできたんじゃないかなと思って、僕はなんか、上がりましたね。とてもいい感じで、気持ちがアップしました。嬉しいですね。」
「一水会」顧問 鈴木邦男さん

1組目は、一水会の顧問をされている、鈴木邦男さん。福島県生まれの政治活動家で、最近では「ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク」の共同代表も務められています。
坂本「あのー、鈴木邦男さんをお迎えしまして。去年は、2回に渡って鈴木さんと対談をさせて頂いて、それがひとつの本になって、発売は1月の下旬だそうですけど『愛国者の憂鬱』という、とても楽しみにしておりますけども。」
鈴木「僕も、ものすごく勉強になりました。去年1年は坂本龍一イヤーでしたから。ええ」
坂本「最初に鈴木さんにお会いしたのは、脱原発の官邸前のデモでしたね。偶然、お隣に、石垣に座られてですね(笑)。たくさんの市民の方が参加されてたんで、僕も市民のひとりとして参加しようと思って行ってみたんですけども、良かったです。」
鈴木「坂本さんがいるなんて思ってもいなかったですね。びっくりしました。」
坂本「随分、世の中が変わりましたね。たった1年半で。やはり何かこう問題があったら、市民が選挙を通してだけでなく、いろいろな方法で声を挙げるっていうのは民主主義の基本だと思うので、それはデモに限らず何でもそうですけども、よくイギリスなんかですと公園で小さな台に乗ってひとりでスピーチをしているような男性なんかも居ますけども、それもひとつの形だと思いますし。ひとりで声を挙げるというのが、日本ではまだ根付いてないと思いますけども、何年に一回の選挙だけ、という、その意思表示の仕方が限られているというのは、おかしいなと思いますね。」
鈴木「政党に投票するんだって、あらゆる問題含めてその政党に投票してる訳じゃないですからね。だから個々の問題については、僕は住民投票やったり国民投票やったり、いろんな形でこう問うべきだと思いますけどね。でないと、どんどんどんどん選挙離れしてしまうし……」
坂本「この選挙制度というのも、非常に問題だなと感じています。つまり民主主義とはそういうものなのかな、その……100というものが全体だったときに、51取れば、100ぜんぶ取ってしまう訳ですよね。そうすると49の意志っていうのは、無いことになってしまう。これのもっと何ていうのかな、巧妙な手口っていうのが小選挙区制で、こないだの選挙のですね、得票数から見ていくと、例えば自民党と公明党に入れたひとの数っていうのは、10人のうち1.5人くらい。むしろ野党全部の方が多いんですね。で、一番多いのが棄権したひとで、これが5人ぐらい居ると。だからここが一番マジョリティな訳ですけど(笑)。だからこの1.5しか取っていない政権が、全権を委任されたと勘違いして、好き放題やってるというのが現状なんですけど、これをどう鈴木さんはご覧になってますか。」
鈴木「小選挙区にしたのが一番悪いと思いますけども、それと同時になんかこう、政治家にだけ頼ってしまう日本人の悪い、僕らも含めた愚かさみたいな。だから、選挙のときに、なぜ棄権したんですかってそのテレビで聴いてたんですよ。そしたら聴かれたひとが「いや、我々を指導してくれる政治家が見当たらなかった」と。指導してくれる……だから、誰かに指導してもらいたい、引っ張ってもらいたい。そんな形を取ってるのかな。僕らが学生の頃は、学内でストライキをやって声を挙げたり、俺たちは政治家に頼らないと。俺たちが世の中を変えてやるんだ。みたいな、デモをやったり集会をやったり、そういう意気込みがありましたよね。そういう気概がないんじゃないかと。自分たちは投票だけする、あとは国会議員が決めてくれるんだ、と。でまた、国会議員も「デモなんかやるのは民主主義じゃない。あれはテロだ」と。国民から選ばれた自分たちだけが全てを決めるんだ、なんて思い上がってますよね。」
坂本「ほんとはその有権者全員で討論して決めればいいんでしょうけど、物理的にはできないので、なので代議員を、代理の者を選んで、代理同士で話し合って物事を決めさせるっていうのが、代議制の民主主義ですよね。ですから、自分たちの意見を反映して、国会で物を言う人たちですよね。だから自分たちがむしろ、使っているっていうのが本来の姿ですよ。だけど、どうもその "代議士先生様" みたいな、手をこすったりするようなね、こういう構造になっていますから、やはり上に立ってるんでしょうね。これはもう本当はおかしいと思いますね。」
坂本「現状のことを言ってると尽きないんですけども、そもそも鈴木さんは、右翼と言われる立場なんですけども、主にその保守的な、あるいは右翼的な人っていうのは、原発推進の人が多いですよね。」
鈴木「えーとね、ひとりひとり聴くと、そうでもないんですよ。なんかね、戦後の右翼というのは、共産党が一番の敵だったんですよ。世界の共産主義運動……ソ連とか中国とか、そういう恐怖が大きかったんですね。だから左翼に対する戦いが、我々の日本を守る戦いだと思ってたんですね。だから左翼の言ってることには全部反対すればいいんだ、と。僕らも昔、錯覚したことがありました。だから、原発も左翼が反対してるんだから、じゃあその逆のことを言えばいいんだと。そういう非常にアバウトな発想でやってて、ただ、震災があってから、これは日本の国土そのものも破壊するんだと。それでかなり考えが変わった人たちが多かったですね。竹島や尖閣や北方領土を守れと言うのと同じように、東北を守らなくちゃいけないと。そういう事で、これはおかしいじゃないか。と、脱原発のデモだとかも起きてきたし。」
鈴木「ただ、今更、脱原発やれないみたいなメンツがあるのと、そんなことをやることによって、左翼を律する事になるんじゃないかと(笑)、まあいま律するような左翼いないですけどね。そういう意味でこう、誤解されてる分が多いですね。」
坂本「ということは、右翼でも原発推進って言ってる人もいる、それは経済がっていうような事を言ったりしますよね。僕は想像するのは、やはり、日本の国土とか、郷土愛とか、日本人という民族性への愛とか、そういうものに基づいた感情から来てるんだと思うんですけど、郷土愛よりも経済が勝っちゃう、お金の方が大事っていうのは、右翼的じゃないような気がするんですけど、どうでしょう。」
鈴木「おっしゃるとおりです。経済発展よりも日本を守る。それこそ、貧しくとも自分たちの思想を貫くというのが右翼の発想だったはずなんですけど、だんだんとね、いわゆる保守……保守主義と右翼の区別がつかなくちゃっちゃって、今の状態を守っていくのが愛国心だと。その点、三島由紀夫なんかは、愛国心という言葉が嫌いだと言ってるんですよね。我々は憂国であり、国を憂う革新であると。」
坂本「だから、ほんとに愛国心を貫くならば、もしかしたら現状打破するような事も起きるとも限らない。ということを含んでいる訳ですね。」
鈴木「だから今ね、いろんな人たちが自分を保守主義者だと、誇りをもって言うことに対して、僕はものすごい違和感があるんですよ。というのは、僕らが学生の頃は、左翼はもちろん革命勢力ですね。それに対する右翼だって "革新" だったんですよ。自分たちは保守じゃないと、自分たちはこの日本を守るんじゃなくて、この世を変えるんだと。ただ左翼のやり方と違うんだと。だから右翼と左翼の人たちの中で、一番軽蔑された言葉が "保守" だったんですよ。それが今、堂々とみんな保守だって言われてるので、ものすごい違和感があったんですね。僕はいい意味での保守は必要だと思うんですけどね。日本の素晴らしさを保守していきたいというのと同時に、日本の間違った事とか失敗した事もいっぱいある訳ですからね。それは個人にだってありますからね。それなのに、自分の間違った事は認めながら、それが集団となった日本については一切認めないと。で、日本は間違ったことは別にない、中国、韓国が悪いんだ。憲法が悪いからこうなったんだ……と、一切認めないと。それは愛国心じゃないですよね。自分たちの過去を見つめる勇気がないんだと思いますね。僕は、日本ではいろんな失敗や抗弁できないような事もあったろうし、それはきちんと謝って、その上で、そういう日本を愛しいと思うのが愛国心だと思うんですよね。」
坂本「そういう鈴木さんのようなまともな意見に耳を開くような、右寄りの方たちっていうのはいらっしゃるんですか。」
鈴木「ええ、居ますけどね。まだまだ僕なんか、そういうこと言うと、左翼だとか、転向したなんて言われます。」
坂本「鈴木さんにとって、自分個人という存在とですね、日本国という国家の存在と、どちらが上に来るのでしょうか。」
鈴木「おー、なるほど。僕は個人あって国家があるんだと思います。国家があって、国家のために死ぬために、ひとりひとりが生まれてきたんではないと思います。思い上がりかも知れないですけども、国家が強くなれば個人が強くなる……そんなことないですね。福沢諭吉が言ってるように "一身独立" 。ひとりひとりが独立して、はじめて国家が独立するんだと。それなのに国家が強大な軍備を持って、素晴らしい憲法を持って、それで政治家にだけ頼ってる国民たちひとりひとりが強くなるか。かえって弱くなりますよね。」
坂本「今日は鈴木邦男さんに、お好きな曲を1曲選んでいただいたんですけども、中島みゆきさん、お好きなんですか。」
鈴木「結構ね、学生運動出身者は好きなんですよ。これは俺の事を歌ってるんじゃないかってみんな思ったりするんですよ。勝手に思い込んでるんですね(笑)。」
坂本「そうなんですね(笑)。吉本隆明さんも中島みゆきさん、大好きでしたよね。」
音楽家・政治活動家・社会活動家 三宅洋平さん

坂本「先の参院選ではですね、ネットを使った『選挙フェス』という新しい形の選挙活動で注目を集めました。2015年の全国統一地方選挙ではね、選挙に行こう!ではなく、選挙に出ようという活動もされているので、どういうことなのか。すごく楽しみなんですけども。僕はYouTubeなんかで、選挙フェスみたいなものや彼のスピーチとかを聴いてて、ほんとに感心したんですけど、やっぱりミュージシャンだからですかね、弁舌さは、いちいち論が立っていてですね、ほんと頭いいんだなと思いまして、僕と大違い。」
坂本「三宅さんはベルギー生まれなんだね。」
三宅「そうです、親父がいわゆる当時の企業戦士と言いますか、海外飛び回ってたんで。7歳で日本に帰国しました。」
坂本「じゃもうフランス語は忘れちゃった。」
三宅「フラマン語だったんですけど、ケンカで使ってた汚い言葉だけは覚えてるんですよ、バカヤローとか。不思議なもんで(笑)。なんか人間の脳みそは9歳まで居ないと、言語が脳に定着しないらいしいんですよね。で、7歳ぐらいだと、その後の日本語のインパクトが入ってきてるんで、抜けてるんだけど、バイリンガル脳ができてるから、英語の勉強は人よりは早かったですね。」
坂本「でしょうね。文法構造っていうかさ、バイリンガルとかトリリンガルっていうのは、異なった体系を行ったり来たりする……そういう能力なんで、ひとつだけの言葉で考えてるのと、ふたつ以上あって、それを行ったり来たりできるっていう……通路、ルートみたいなところ。そこが多分、強くなるんでしょうね。」
三宅「それって言語を越えて、思想に大きく影響を与えてます、うん。だから7歳で日本に帰ってきて、カルチャーショックと言えば、そうだったんですけど、憧れてたんですよね。自分が祖国に帰るっていう意識があったんで。ところががっかりしたんですよ、帰ってきて。それは何がっていうか、日本社会の醸し出す雰囲気、大人たちの……」
坂本「もう既に感じてたんだ、面白いね。」
三宅「感じましたね。そこからが、僕の中で既に精神的な細胞分裂が始まって、今でも思うんですけど、やっぱり日本社会の持ってる特殊な閉塞性っていうのは、もう少しそこの、ある種のバイリンガル脳というか、言語教育もあるんでしょうけど、ブレイクスルーしたいところだなあと思いますね。」
坂本「なるべく早いうちに、まあ10代なんかのうちに、3ヶ月でもいいから、世界をほっつき歩く体験をなるべくしてほしいですよね。」
三宅「あるいは、ものすごい恵まれた裕福な家に生まれつつ、若い頃にブルーワーカーに僕なんか憧れて、僕なんか中産階級なんですけど、現場仕事とかに憧れて、わいわい親方とかにしごかれてんのが好きで、当時、読んでたのがジャック・ケルアックとかのビートだったんで、なんかこう、ブルースを奏でるにはこういう世界に居なきゃ駄目だし、自分のこの柔な育ちじゃ駄目だっていうことで、一生懸命、自分を汚す作業をその頃して、それもやっぱりひとつ大きな、世の中を見る目が変わる……母親なんかには、弁護士だとか、医者だとか学者になれと言われて育ちながら、結局、そういう人たちの方がどこか人として輝いてる部分も感じるし、一方でその、アスベストだの何だのって過酷な労働環境で、芯から出るような咳してる親方の背中見ながら俺は三ヶ月の短期バイトで、彼らに対する想いというか、必要以上に哀れんだら絶対怒られるんですけど、やっぱりもっとその社会の大動脈になってる人たちに、もっと優遇というかもう少し生活の改善をしてもいんじゃないかなってのは、今でも根っこにありますね。」
坂本「趨勢として反対の方向に来てますよね。」
三宅「人間ひとりの重さがどんどん軽くなっていくっていう。」
坂本「三宅さんも、あちこち世界を旅したり見てると思うんですけど、やはり国によって、人間ひとりの重さが随分違ってるところがありますよね。」
三宅「為替制度ってだからそう考えると、人間の価値をね、ひとりの人生の時間と言うか……インドネシアの場末の工場で働いている30人の一生分の時間と、日本のサラリーマンのひとりの一生分の時間が等価で清算されてしまうとかっていうのは、根本的にやっぱ人権問題に繋がるんで、ただ、じゃあ為替制度をなくすのかという議論ができる程、僕がまだそこの経済的な見識が追いついてないんですけれど、ただそれは、どこか日本社会は、確かっぽい事じゃないと口にしてはならないという風土が存在してるので、つまり自己検閲がきついんですよね。ところが僕が経済について、専門家ではないのにそういう事をよしんばつぶやいたとして、何が起きるかというと、詳しい人たちがボコボコに叩いてくれるんですよ。これがね、一番、学習速度が速いです(笑)。」
坂本「(笑)なるほどね。はー、そっか。」
三宅「そうなんすよ、だから批判する人が教えてくれるんで、僕ん中ではある意味それはノマドな秘書だなと思って、こんな言い方したら誰も相手してくれなくなっちゃうかもしれないですけど。みんなを代表してハテナを発する、っていうのも政治家の仕事かもしれないすね。」
坂本「選挙は2年半くらいですよね、今度は都知事選があったりするんですけども、このまま選挙活動っていうのかな、選挙フェスかな、今後も続けていこうと思っているんですか、今。」
三宅「あのー……いろいろな形で、いかに日本人の生活の中に、携帯代を払うような感覚で毎月、自分の意中の候補者に8,000円献金する。とかいうことを定着させていきたいんですよね。」
坂本「クラウドファンディングみたいですね。」
三宅「そこをいかにカジュアルにするか。っていうのは、何か今まだ発想の転換というか、"個人献金" というワードに籠る概念そのものを変えなきゃいけないと思うんで、だからクラウドファンディングっていう言い方もいいだろうし、あるいは、あえて個人献金という言い方のまま、いろんな……」
坂本「個人献金というイメージを拡大しちゃう、拡張しちゃうっていうことですよね。」
三宅「そうすね。そんなような事をあらゆる局面に於いて展開していきたいなあとは思ってるんですけど。」
坂本「だから単なる選挙活動じゃなくて、やっぱり意識改革をやろうとしてるんでしょ。」
三宅「当選しても落選しても、政治家であろうがあるまいが、もっと愛があるいい社会を作るということを急ぎたいんですよね、ひとりの者として。それはある意味、政治家であるとか音楽家であるということを越えていて、ひとりの者として、やれることはやり切りたいなというとこすね。」
坂本「そういう風にフォーカスが絞られてきたのは震災が大きいんですか。」
三宅「そうですね、うん。震災以前に、反原発の現場にたびたび立ち会って思うところがいっぱいあったんですよね。つまり原発を推進する保守性もだし、それから反原発運動に宿る保守性も、両方、僕には同じに見えたんですよ。」
坂本「僕も、何回か行ったことありますけど、引いてしまいますよね。」
三宅「おしゃれじゃないと、僕、無理なんでっていうのは、すごく言ってきたんですよ。もうちょっと砕けた時代にしたいなとも思うし、だから戦国時代に、千利休という人が出てきて、武の時代から侘び寂び、乙の時代になるんだこれからはっていう事をあれだけ拡散したのは、まそりゃ最終的に武力の権限の長たる者に殺される活動だなあと思うんですけど、あれは平和運動だと思うんですよね、ある種の。とても狡猾でとても政治的な。だから僕ら文化人の果たすべき役割っていうのは、やっぱ、あの時代の利休のような意識で……」
坂本「最高の武将たちに刀をそこに置かせて、お茶のためだけに部屋に入ってくるというような空間、あるいはそういう作法を作ったっていうのは凄いですよね。武器よさらばですよ、ほんとに。」
三宅「そうなんですよ。一番、武に憂いてるのは武将そのものだったはずなんですよ。命のやり取りの時代を終えたいと。だから家康が掲げたキーワードが "天下泰平" っていうのは、僕はある種、心からの思いなんじゃないかなって、思いますよ。」
坂本「まあ、家族みんな殺されてますからね。で、家康は非常に健康オタクで、漢方とかを自分で煎じたりしていて、大きな棚にいろいろ入れてたらしいんですけども、とにかく、長生きするんだと。生(せい)っていうこと、生きるってこと、にとっても執着してたっていうのは、やはり死の戦国時代だったからでしょうね。まわりに死がたくさんあったからでしょうね。とにかく生き抜いて、天下泰平にするんだと。もちろん負の側面もたくさんある訳ですけど、まあすごい人だなと思いますね。」
三宅「僕、最近ちょっと見直してます。あんまり歴史好きの中学生が好きになるタイプじゃないじゃないですか。」
坂本「(笑) かっこよくないじゃないですか、やっぱり織田信長とかの方がさあ。だけどね……かっこ良くないんですよ、生きるってことは、うん。」
三宅「うん。そこをね、この放射能時代と言いますか、生きるという事がここまで差し迫ったテーマにもう一度なったっていうのは、一方でね、長い目で見たときには、すごく尊いテーマを人類は授かったなと思うんですよ。原発でも爆発しなければ、我々は価値観を越えてひとつになろうとしなかったであろう。って、後年、語られるような出来事にできるかできないかっていうトライだなと思っています。」
坂本「あのー、YouTubeとかね、三宅さんの演説って言っていいのかな、スピーチを聴いてるとね、ほんとに流暢で淀みなくいろいろ出てくるんですけど、で、言ってることもとても素晴らしいんだけど、そういう訓練をしてる訳。」
三宅「思い当たるのは、お袋が、僕がまあ外国生まれってことで、日本語教育にすごく重きを置いてて、いま思うと、5歳くらいで小2ぐらいのことを日本の子はみんなやってるという立前でやらされてたんですよ。あとは台所で夕飯を作っているお袋の後ろで、本を抑揚つけて音読して、ご飯が出来上がるまで読み続けるっていうのをね、小1、小2くらいまで毎日やってたんじゃないですかね。」
坂本「最低でも1時間くらい……」
三宅「つっかかったら次の人に代わるっていう国語の授業があったんですけど、僕が読み出すとベルが鳴るまでつっかからないっていうので、最後に拍手が起きるっていう、鳥人間コンテストみたいな、おーっていう。いま思えば演説の原型がそこにあって、そういう訓練は確かにしたのと、あとは自分自身はシンガーとして出発したとは思うんですけど、やっぱりスポークン・ワード、ラスト・ポエッツとかギル・スコット・ヘロン、まあ歌とも、シング・ライク・トーキング、トーク・ライク・シンギングな……」
坂本「ギル・スコット・ヘロン、好きなの。僕も好きだったなあ」
三宅「あの感じがすごくかっこ良くて、あれはやっぱり憧れたんですよ。で、白人のポエトリーの音読と黒人のポエトリーの抑揚の差、やっぱりブラック・ポエットのかっこ良さっていうのは、その、音楽性にあったんすよね。」
坂本「あのー、ミュージシャンで亡くなる方も最近多いですけど、僕は元々はクラシックをベースにやってたんですけど、クラシックなんかだと、ほぼ聴いてるのは、もう既に何百年前に亡くなった人たちの音楽なんですよね(笑)。だけど、そういう250年前に亡くなった人が作った音楽……から勉強し、あるいはそれと対話し、自分の栄養になってってやっているんですね。でも音楽ってそういうものかなと。例えば、村で長老が民話を伝えるっていうのも、何世代も前から亡くなった人たちの言い伝えを少しずつ変形しながら伝えていくというようなもので、もともと文化ってのは、そういうものだったのかなと思うんですけどもね。そういう形っていうのは残してかないとって思いますね。」
三宅「特に、無形の物を受け継ぐことの意味が大っきいので、古文書とか記録書っていう文字化された歴史は必ず湾曲するし……」
坂本「やっぱり口伝ですよ、口伝、ね。」
三宅「そうなんですよ。口伝には嘘が混じらない。むしろ。」
BRAHMAN TOSHI-LOWさん

坂本「3組目は、ミュージシャンのTOSHI-LOW君ですね。茨城県水戸市の出身で、BRAHMANのフロントマンですけども。寡黙だった彼が311以降、LIVEのMCなんかで積極的に発言をしてます。2012年の『NO NUKES』のフェスをやったときに僕は初めて会ったんですけども、何て乱暴なヤツだと思ってね(笑)、なるべく近寄らないようにしてたんですけども、本当の彼はどうなんでしょうか。ゆっくり話します。」
坂本「えーっと、まあこうやって、ふたりで話すのも、ほとんど初めてに近いんですけど、TOSHI-LOWさんです。」
TOSHI-LOW「えっへっへ(笑)。俺あれですよ、2012年のNO NUKESのイベントの打ち上げで、最後、教授に怒鳴られて以来ですよ。」
坂本「怒鳴ったっけ(笑)。最近、怒鳴ってないんだけど(笑)。」
TOSHI-LOW「(教授が乾杯の挨拶するときに騒いでいたら) うるせー、このやろーって(笑)。あれ楽屋に帰ってからメンバーに褒められましたからね、世界のサカモトに怒鳴られたぞって。」
坂本「初対面のときはね、サウンドチェックだったのかな。ステージ脇で、何だよ、いるよいるよなんて言ってたよ、俺のこと。」
TOSHI-LOW「何がですか、あっはっはっは(笑)。だって画面の中の人で、なぜ俺たちYMOと対バンするのか、何となく解らない状態のまま来てしまったので、ほんとに居たと思って。」
坂本「しょっちゅう、酔っ払ってる。」
TOSHI-LOW「しょっちゅう酔っ払ってます。俺、今日、たんこぶ……ここ触ってもらっていいすか。」
坂本「あれ。見えるね……どうしたんですか。」
TOSHI-LOW「解んないんですよ(笑)。昨日、渋谷で飲んでて、途中まで覚えてて "ロックバンドなのにすごい同期を使ってるバンドに、全然グルーヴ感じねえよ" みたいな事を言った辺りまでは覚えてんすけど、そこからこのたんこぶは謎なんすよね。気づいたら家で寝てましたね。」
坂本「お父さん、なんですか。」
TOSHI-LOW「パパですね、あのー、はい。小学校2年生と、1歳半の男が2人います。」
坂本「福島を何度も行ってるでしょうし、震災の復興を一生懸命やってるんですけど、東京も場所によっては線量が高いなんて情報もあって、心配じゃないですか。」
TOSHI-LOW「心配……なんすけど、なんかやっぱ、いっしょに居たいすね、家族を。これどこまで言ってあれなんすけど、前の彼女みたいな子がいて、その子は環境的に意識が高い子だったので、震災あって原発爆発して20日くらいにすぐ、友達たちとハワイに行ったんすね。そしたらオワフの空港で、ここの動脈ばつんと、そのまま死んだんすよ。それが3月20日くらいだったから、あの東京の中で崩れ落ちて、もうそういう事だらけで、またちょっと別だなと思って。疎開するっていうことと、だったら……俺、子どもに聴いたんすよね。正直どうする、行けるよ、俺、友達いっぱい居るから、一緒に居ることもできるけど、どうしたいって言ったら、一緒に居たいって子どもが言ったんで、だから、子どもの意思を尊重したかったつうか。」
坂本「福島や、いろんな事情で避難できない人もたくさんいる訳だけれども、親の痛みっていうのがほんとに、ちょっと想像できないよね。」
TOSHI-LOW「苦しいすね、ほんと。福島なんかは特に。」
坂本「そういう人たちに、どういう風にやったらいいですかね、僕たちは。」
TOSHI-LOW「どうなんでしょうね。一生、福島と付き合って……僕は実家が茨城なので、んで、うちの親なんかは野菜をやっているので、もろですよね。もう売り上げは全然戻ってないし、うちの親父もへこんでるというか落ち込んでるんすけど、報道されてないことがあり過ぎて、茨城の農家でも自殺してる人とかいっぱいいるので、とにかく、自分の場合は、現地行って、見たものを自分なりに発信していくっていうことが……」
坂本「やっぱりその、福島っていうのは海外でも有名になってしまったしね、まあ不幸にも。あんまり福島、福島って言うと、福島だけの問題のようにみんなが思っちゃうというか、そういうジレンマもあってね。関東も線量が高いところもあって被害も受けている訳なんで、あまり福島だけ、東京は関係ないと思ってほしくないんですよね。」
坂本「福島以外の、岩手とか宮城とかもよく行ってるんですか。」
TOSHI-LOW「よく行ってますね。バンド仲間とライブハウスを作ったんですよ。岩手県の宮古市と大船渡市、宮城県石巻市っていう3つ、45号線ってあの海沿いに、うちのPAが中心になって作りまして。キャパ的には200ぐらいの小さい所なんですけども、やっぱその45号線をバンドマンが回れるように、そして見て、またはその全国のそのバンドが好きなファンの子がまたそこに来て、初めて東北に触れてみるっていう機会になるんじゃないかなと思って、そこに力を入れて結構やってきたんですけども。だから三陸と触れ合ってるとすごい楽しいんですけど、福島はまた別個な感じがしますね。」
坂本「あー、でも偉いねえ。」
TOSHI-LOW「で、福島も猪苗代湖に野外音楽堂を、その流れでもう1個作るっつうのを、あの箭内道彦っていう……」
坂本「はいはいはい、風とロック。」
TOSHI-LOW「そうそう、金髪のあれといっしょに組んでやってるんですけど。」
坂本「だけどまあ、中国でも大きな地震があったり、ハイチでもあったり、毎年のようにフィリピンで大きな台風の被害があったりとか。東北にこれだけシンパシーを持ってやるっていうのはもちろん大事だけど、他の所もいろいろある。自然災害だけじゃなくてアフリカのスーダンのあたりで凄いことになってたり、尽きないですよね、世界には問題が。全部付き合っている訳にはいかないし、だけど、じゃあどれかだけっていうのも不公平だし、どうしたらいいのかな。って、僕もよく思うんですけど、何か方針ありますか。」
TOSHI-LOW「なんか、俺、こういう、そういうのも縁なのかなって思ってまして。例えば今日、教授に会って、俺の知らない世界の悲しい事を知って、TOSHI-LOWこれやってみない、って言われたら、何かやるんだろうなっていう事を、できるだけ自分もオープンにして、やってけたらいいなと思ってますね。」
TOSHI-LOW「世界って、ずっとこんな感じなんすか。」
坂本「世界ってずっとそうですね。いつもありますよねぇ。」
TOSHI-LOW「初めからでも、教授もあれでしょ、その、何だろ……」
坂本「うん。いや、同じこと質問したかったんだけど、震災前はどうだったの。」
TOSHI-LOW「はっはっはっは(笑)。いやもうね、10代で音楽入ったのが、パンクから入ったんすよ。なので、なんか東京に来て、またちょっとそこが音楽をこうやってるときに影を潜めてしまって、なんだろ、心はあるんですけど、それをもっと対自分の方に深く持ってったのが20代だったんですけど、なんかもっと震災でもっと自分の涌き上がるものがいっぱい出てきまして、わー、俺こんなためにサラリーマンみてえなミュージシャンなるために東京来た訳じゃねえし、音楽やってる訳じゃないってことに、もう一回気づいてしまって、でその前にちょっと辞めようと思ってたんで(笑)。」
坂本「あそうなんだ。別にパンクに限らないかな、その社会的なその……善い行い、善意みたいな事ってさ、かっこ悪いよね。」
TOSHI-LOW「かっこ悪いと思ってましたね。」
坂本「だよね。やさぐれっていうかさ、反社会的な方がかっこ良いものね。でも、そういう人でも、ちゃんと心の中の方を覗いてみると、ちゃんとそういう心があるっていう事だよね。」
TOSHI-LOW「もう、入れ墨だらけのバイカーが、現金と支援物資を持って俺のまわりも行ってる姿を見てたので、やっぱそういう事なんだと思います。」
坂本「だから人は見かけで判断しちゃいけないんだよね、ほんと(笑)。僕もTOSHI-LOWを見て、何て乱暴な奴かなと思ってたけど、でもね、すごいシャイだしね、優しい奴だよね。偉いなだけど、45号線の話は。で、地元の人たちは来るようになったの。」
TOSHI-LOW「なってますね、うん。一番嬉しいのは、高校生のバンドがちょっと増えたりっていう。そしたらそいつらが、来たときに俺たちと対バンするんだろうって思うだけで、ちょっと俺は沸きますね。」
TOSHI-LOW「でも東北って、ぜんぶ、ぜんぶ被災なんじゃねえかなってちょっと最近、思ってて。なんか、三陸と付き合う程、東北がもともと抱えてた闇というか、東北に追いやってしまった……六ヶ所の問題でもそうだし、貧富の差でもそうだし、自分たちが知ってるようで知らなかった根深さに気づいていくというか。」
坂本「明治維新のときに戊辰戦争ってのがあって、ちょうど、終わったばかりだけど、NHKの大河ドラマ『八重の桜』の話だったんですけど、負けた側ですよね、東北がね。で、実はその前から、大和朝廷の時代から、東北っていうのは征伐の対象でね、東北征伐をしに行く大将を将軍って言ってたんですよね。」
|
今回の『新春放談』はポッドキャストで、2014年1月6日12:00より配信します。 |
|
|
■『愛国者の憂鬱』を5名の方にプレゼント!
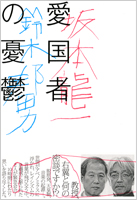
今回は、坂本龍一、鈴木邦男の対談書籍『愛国者の憂鬱』を5名の方にプレゼントします。
番組の感想やメッセージも、ぜひお書き添えのうえ、コチラからご応募ください(教授と番組スタッフ一同、楽しみにさせていただいてます)。当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます。
|
|
|