




「坂本龍一です。2ヶ月に一度お届けしているレディオサカモト。皆さん、ご無事でしょうか。この2ヶ月、コロナウィルスの影響で世界が一変してしまいました。僕は3月にこの番組を放送した後、しばらく日本にいましたけどもね、4月頭にニューヨークの自宅に戻ってきまして、そこから2週間、隔離生活をしていました。もう隔離生活は明けたんですけども、未だに1歩も出ていませんね、外に。まぁ、そんなに普段(これまで)と変わらないんですよ、実はね。普段もほとんど引きこもっているので、オンラインでやることが結構たくさんあるので、結構忙しいんですよね。まぁあの、どこか現場に行かないと出来ない仕事というのもたくさんあるわけですけども、えー、僕なんかはその、自宅で音楽が作れるので、本当にラッキーな仕事だと思います。僕の周りの音楽に関わる人達でも、舞台を作る人とかですね、照明を作る人、音響を制作する人、などなどはですね、まぁそれからライブハウスですよね。あるいは映画館、劇場……劇場もたくさんの人が働いているわけですよね。そういう人たちが本当に大変で、望むべくもないんですけど、本当にドイツのように文化に対してきちんとこうね、リスペクトをして欲しいものですけどもねえ、まぁ難しいのかな。だからって、そう言っちゃいけない、ちゃんと言わないとね。」
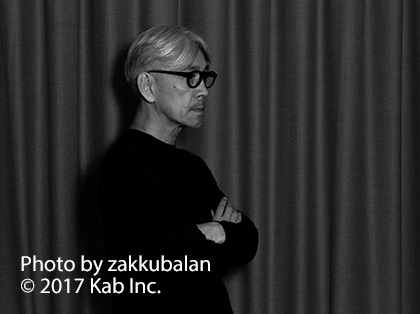 「4月の頭頃にニューヨークに帰ってきて、その頃っていうのは、まだピークに向かっていた頃かな。ピークが確かね、15日ぐらいだったと思うんで。まだまだ、どんどん感染拡大してるニューヨークに帰るっていうのはどうなのか、随分周りに反対されましたけどね、実はね(苦笑)。あの心配してくれたわけですけど、みんなね。あんまり人がいないところに、道に来いとかっていう有り難い話も頂いたんですけど、あの……まぁ、日本にいてね、東京でホテルに泊まってるんですよ、家がないんで。それもちょっとプライバシーの話をしちゃいますけども。で、ホテルに泊まってる。で、万が一、東京で僕が感染して熱が出たら、ホテルが困るんで追い出されちゃうわけですね。で追い出されて、じゃああの短期で急遽マンションを借りる、これもやっぱり熱が出てる人は貸してくれないわけですね。で、路頭に迷う、もし感染したら。でもう僕は、発表される感染者数、数っていうのは全然信用してなくて。結局その、当初はクラスター対策うまくいっていますって言ってましたけども、発表では、僕は全然信用していなくて。まぁ確かにクラスターで追っかけられた部分もあるでしょうけども、それをやってるうちに、市中感染、見えない街なかの感染がどんどん広がっているに違いないと僕は確信していたので、でそれは今となっては事実というかね、クラスター対策班の専門家の方達が、事実上、うまくいかなかったというようなことも認めてらっしゃるそうですけども、僕は見えない市中感染がひどいと思っていたので、日本にいても、ニューヨーク州の方針になるべく沿ってですね、行動してたりとかして。でもまぁ本当に分かりませんから、日本にいて感染するかもしれない。そしてもうどこにも行きようがないっていうんで、どうせ隔離生活するんだったらば、やはり自分の家でしたいよねっていうんで、まぁあの、本当に結構……決断してニューヨークに帰ってきた。で、ニューヨークは感染がまだまだ拡大している途中で、本当に1歩も出ないで、かなり緊張状態ではありましたね、やっぱりね。で、今の状況でいうと、だいぶピーク時からは下がってきて、いろいろな死者数とかですね、新しい日毎の感染者数とか、入院者数とかですね、それぞれの数字がどんどんどんどん下がってきてはいますけども、それでもまだ一日に300人以上の方が亡くなってるというのが、本当にそれでも異常事態ですよね、一日ですからね。いやぁ、でもこの話はキリがないですね、すいません。」
「4月の頭頃にニューヨークに帰ってきて、その頃っていうのは、まだピークに向かっていた頃かな。ピークが確かね、15日ぐらいだったと思うんで。まだまだ、どんどん感染拡大してるニューヨークに帰るっていうのはどうなのか、随分周りに反対されましたけどね、実はね(苦笑)。あの心配してくれたわけですけど、みんなね。あんまり人がいないところに、道に来いとかっていう有り難い話も頂いたんですけど、あの……まぁ、日本にいてね、東京でホテルに泊まってるんですよ、家がないんで。それもちょっとプライバシーの話をしちゃいますけども。で、ホテルに泊まってる。で、万が一、東京で僕が感染して熱が出たら、ホテルが困るんで追い出されちゃうわけですね。で追い出されて、じゃああの短期で急遽マンションを借りる、これもやっぱり熱が出てる人は貸してくれないわけですね。で、路頭に迷う、もし感染したら。でもう僕は、発表される感染者数、数っていうのは全然信用してなくて。結局その、当初はクラスター対策うまくいっていますって言ってましたけども、発表では、僕は全然信用していなくて。まぁ確かにクラスターで追っかけられた部分もあるでしょうけども、それをやってるうちに、市中感染、見えない街なかの感染がどんどん広がっているに違いないと僕は確信していたので、でそれは今となっては事実というかね、クラスター対策班の専門家の方達が、事実上、うまくいかなかったというようなことも認めてらっしゃるそうですけども、僕は見えない市中感染がひどいと思っていたので、日本にいても、ニューヨーク州の方針になるべく沿ってですね、行動してたりとかして。でもまぁ本当に分かりませんから、日本にいて感染するかもしれない。そしてもうどこにも行きようがないっていうんで、どうせ隔離生活するんだったらば、やはり自分の家でしたいよねっていうんで、まぁあの、本当に結構……決断してニューヨークに帰ってきた。で、ニューヨークは感染がまだまだ拡大している途中で、本当に1歩も出ないで、かなり緊張状態ではありましたね、やっぱりね。で、今の状況でいうと、だいぶピーク時からは下がってきて、いろいろな死者数とかですね、新しい日毎の感染者数とか、入院者数とかですね、それぞれの数字がどんどんどんどん下がってきてはいますけども、それでもまだ一日に300人以上の方が亡くなってるというのが、本当にそれでも異常事態ですよね、一日ですからね。いやぁ、でもこの話はキリがないですね、すいません。」
「でもね、ニューヨークに帰ってくる前、4月頭まで、まぁその4月2日に外出自粛している方達の為に、オンラインのLIVEというのをやりましたけど、翌日3日、4日というのがね、まだちょっと発表できないんですけども、急遽、録音したくなった内容がありまして、そのレコーディングを最少人数で、あるスタジオで2日間やりました。ま、それは今年の後半でも発表できる、出てくると思うんで、また追々発表しますけども。」

<村上龍さんから最新作とメッセージが届きました。>
「(村上龍さん) えっと、消耗品は、何年続いたんだっけな、凄く続いて、連載のいちばん最後の作品です。MISSINGは、私小説みたいなんだけど私小説じゃないっていう不思議な小説で、自分でもこんなの書いたの初めてだと思いました。坂本……は、坂本だより (坂本龍一だより) 読んでると、なんか忙し過ぎるんじゃないかなーって心配です。僕は何にもしてないですから(笑)。あんまり忙しくしないで欲しいですね。ってだけです、はい。」
「ええと、まぁあの村上龍ってのは、同じ龍が付いているし、辰年、同い年だし、ということで、そのデビュー作の『限りなく透明に近いブルー』もやっぱり気になってすぐ読んでですね、当初そのブルーに関しては、ちょっと僕はなんかこう反感すら持って、単純に普通の小説として読めなくて、こう……書いてある内容が、わりとその僕たちの20代前半、10代終わりから20代前半にかけての生活とかですね、環境、周りのとかが、そっくりというかな、そっくりっていうわけじゃないけども、かなりその……近い状況で暮らしてて、まぁそういう若い子がいっぱいいたわけですね、当時ね。それで、まぁあの亡くなったり、ドラッグのやり過ぎで亡くなったりとかそういう子たちもいたし、そういうね、周辺のことが赤裸々に書いてあるんで、なんか僕はちょっと反感持ったんですよね(笑)。あんまり世間一般に触れてほしくない、晒したくない、僕たちだけの世界をこう……人の目に晒した、みたいなね(笑)。そういう気持ちが多分あったんだと思うんですけど。でも、まぁ気になってですね、で『コインロッカー・ベイビーズ』が出てまたすぐ読んでですね。ま、『海の向こうで戦争が始まる』も読みましたけど、コインロッカー読んで、コインロッカー読んだ時は、純粋に小説としてすごいと、お話として読み物としてすごいなと思って、それで会いに行ったんですよね、横浜……だったかな。なんか自宅に、インタビューしに行ったんですよ。それがね、本当40年くらいの付き合いなんですけど、後にも先にも自宅に行ったっていうのはね、これだけ長く付き合っているのに1回だけっていうね(笑)、変わった友達なんですよね。普通友達っていうと、何か自宅行ったり来たりお互いに訪ねたり、まぁ結婚したって言ったら、おめでとうって行ったりですね、そういうことがあると思うんですけど、ないんですよね。不思議な付き合いでね。それはそれで、付き合い方も一般的なその付き合い方があるわけじゃないんで、もう本当に個人と個人でそれぞれ、AとBが出会ったら、AとBの付き合い方っていうのが、それぞれみんなある訳だから全然構わないんですけど、面白なぁと思いますよね。こういう付き合いもね。でまぁ折々、あの村上龍の、ご存知かもしれませんけど、映画を作ったりしたりですね、してるんで、音の部分で、音楽とかの部分で一緒に関わったりしたこともありますし、あの、またテレビの番組をやったりしているので、そこに出て行ったりとかですね、いろいろ関わりがあります。で最近は、数年に1回、会ってご飯を食べて、まぁ近況報告というか、雑談をして、なんとなく別れるという感じですけども。で、その村上龍がこの5年ぐらいかけて、えー書いていたのが、この『MISSING 失われているもの』という新しい小説です。これはね、3月くらいに出て、読んだんですけども、ま、僕は「素晴らしい!」という表現はちょっと、違うかな。なんかすごい、すごい小説だなと思いました。どうすごいのかっていうのは、みんな読んで、自分たちで判断していただかないといけないと思う。全然分からないっていう人もいるかもしれないし、人それぞれだと思うんだけど。物は試し、読んでみてください。読まないと分からないんでね。えーと、それで、そうそうそう。この新しい小説MISSINGと、80年代からずっと書いてるんですよね『すべての男は消耗品である。』というシリーズをね。その最終巻というのが出たんで、それをセットにして、村上龍のサインを入れて5名の方にプレゼントするということです。みんな外出自粛で、家に籠もってる人はきっと、非日常的な時間がたくさんあるでしょうから、あの本なんかもたくさんね、日頃読めない本とか、観ていなかった映画とかみんな観てるんでしょう。ぜひ読んでみてください。」


|
■村上龍さん『MISSING 失われているもの』『すべての男は消耗品である。 最終巻』のサイン本をプレゼント!
RADIO SAKAMOTOからのプレゼントです。
今回は、『MISSING 失われているもの』『すべての男は消耗品である。 最終巻』に村上龍さんのサインを入れて頂き、セットにして5名様にプレゼントします。
コチラからご応募ください。
番組の感想やメッセージも、ぜひお書き添えください (教授と番組スタッフ一同、楽しみにさせていただいてます)。当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます。
|
|
|

<きょうの猫村さんのテーマ曲など、近況。>
「えーと、あと4月からね、何日からだったっけな、その『きょうの猫村さん』ていう(笑)、ほしよりこさんの漫画の『きょうの猫村さん』を松重(豊)さんが猫村さんになって、家政婦役をやってるという、非常にシュールなテレビ東京の番組ありますね。週1回で2分半ていう、ものすごいシリーズですね。なぜかそのテーマ曲を書いてくれって言われまして、漫画も好きだったし、面白いと思ってですね書いたんですけど、でも書くんだったら、主演をやる、猫村さん役をやる松重さんに歌ってもらおうと。松重さんというのは、今までレコーディングもしたことがなくて、歌声も僕も聴いたことはないんだけど歌ってもらおう、下手でもいいや……と思ってですね(笑)、無理やりデモテープを作って送りつけて、歌ってもらって、これが中々、低音の魅力でいいんですけどね。これが流れてますね、テーマ音楽として。まぁその曲を作ってくれって言われた時に、歌詞はU-zhaanがいいと。『きょうの猫村さん』のあの、こう捻れたおかしなユーモアのある世界を歌詞で表現できるのはU-zhaanしかいないと思いまして、でU-zhaanも初めて歌詞を、頼まれて歌詞を作ったことがないそうなんですよ。で、松重さんも初めてだし。僕ももともと歌を作るのはうまくないので、全然。みんなが歌えるような歌っていうのは、本当に…ま、知ってる方は分かるでしょうけど、全然うまくできないので、なんとか……歌をやったことがないという松重さんでも歌えるようにと思ってですね、だけどやっぱり、『きょうの猫村さん』だから少し捻りも入れたいというような気持ちもあってですね、まあ出来たわけなんですけども。」
そして番組では、教授が手がけた、長編アニメーション映画『さよなら、ティラノ』のエンディング曲をオンエアしました。
「1曲聴きましょう。今年の初夏公開予定なんですよ……やっと日本でも公開されそうですけども、久しぶりの30何年ぶりの僕のアニメのサウンドトラックですね。『さよなら、ティラノ』という、恐竜が主人公のアニメ映画ですね。で、そのエンディング曲があるんですけど、これは僕からの指名で、コトリンゴとハナレグミに歌ってもらいました。はい、じゃ「楽園をふたりで」、ハナレグミとコトリンゴです。」


<小田香さん、黒沢清さんとの「大島渚賞」トークショー>

「ここからは、3月20日に行われたトークショーの模様をお届けしますね。えーと、このイベントは、『ぴあフィルムフェスティバル』……PFFって言いますね。が、新たに創設した「大島渚賞」。この授賞式の一環で、受賞された小田香監督、そして審査員の黒沢清監督、同じく審査員のまぁ僕、坂本、そして司会役というかな、モデレーターとして『ぴあフィルムフェスティバル』の荒木啓子さんが、厳戒態勢の中で行いました。
残念ながら関係者だけ、報道陣の関係者だけにして、一般の方はいらっしゃらなくてですね、で、しかもその席も1つずつ空けて、そういう形でやりました。まぁね、小田さんについてとか、トークの中で言っているので、まぁ大阪出身……えー関西の方で女性で、受賞したのは小田さんなんですけども、その小田さんの新作『セノーテ』という映画がありまして、それも素晴らしいんですけど、その2年位前にニューヨークで、やはり小田さんの『鉱 ARAGANE』という2つくらい前の作品を観たんですけども、これもあの本当に驚く、びっくりするような映画で、ちょっとショックを受けました。で、実際その時も小田さんにもお会いしたんですけど、ニューヨークで。まぁその時は挨拶程度で、今回はトークということで、突っ込んでいろいろな話を聞くことが出来ましたけども。とてもユニークな方だし、なんて言ったらいいかなぁ。ぜひ、聞いてみましょう。小田香さん。」
坂本「あれは期間はどのくらい現地に行ってたんですか?」
小田「えーと、撮影自体は3週間から4週間を3度、2年の間にしました。」
坂本「2年間。」
小田「はい。なので、大体3ヶ月ぐらいですね。」
坂本「それってその、そもそも、マヤ文明というか歴史も含めて、そういうものに興味を持ったというのは、どのあたりなんですか。」
小田「そういう神話とかは、あの、昔から好きなんですけど、でもあの『セノーテ』のきっかけというか、実際の始まりはサラエヴォで一緒に勉強してた友人がメキシコ人なんですけど。」
坂本「あ、サラエヴォのタルベラの学校でね。」
小田「そうです。はい。で、彼女に「炭鉱の後に何撮りたい?」って聞かれた時に、次は水を撮りたいっていう風に……」
坂本「思ってたんだ、既に。」
小田「はい。水の中で撮りたいっていう風に言ったら、セノーテのことを紹介してくれたんですよ。で、セノーテを調べていったら、マヤの人たちだったりっていうのを……」
坂本「歴史とか背景が分かった。潜りたいんだね、地底とか水の中とか。」
小田「あの…そうですね(笑)。意識的にものすごい、普段から地下に行ってるとかではないんですが(笑)」
坂本「地下好きって(笑)」
小田「でも結果的に、今までそうなってきてます。」
坂本「面白いですねぇ。空には向かっていかないんだね、今のところ。」
小田「空?」
坂本「うん。」
小田「えっと、お金次第なんですが、宇宙を撮りたいです。」
坂本「宇宙?」
小田「宇宙。」
坂本「宇宙?」
小田「はい。」
坂本「おぉ。」
小田「宇宙は撮ってみたいんですけど、でもあの……」
坂本「それは、宇宙から地球を撮る。それとも……」
小田「そうです。地球を撮りたいです。」
坂本「あぁ、なるほど。どんなんなるんだろうねぇ。」
小田「分かんないですね。」
坂本「ねぇ。気球をさ、気球って結構1万メートル以上とかいくじゃないですか。かなり。そこにあの、カメラとかiPhoneとかくっつけて、飛ばすんじゃダメなんでしょう?やっぱり自分で回さないとダメなんですよね。」
小田「そうですね。自分で撮影……撮影が楽しいので。」
坂本「うん。そこの『セノーテ』も自分で、水の中のシーンは全部自分で回してるんですね。」
小田「全ショット、自分で回しています。」
坂本「うん。その為に、ダイビング習ったんですか?」
小田「はい。一応あの、オープンウォーターっていう初級のライセンスだけ取って。」
坂本「タンクを付けて潜るんですか?」
小田「はい。」
坂本「あ、本当。」
小田「本当は『セノーテ』に潜る際は、ケーブなので、ケーブダイバーのライセンスがいるんですけど。」
坂本「あぁそう。」
小田「それを取るには、30〜40回潜らないといけないので、オープンのところで。そこはちょっと…。」
坂本「省略。」
小田「省略させてもらって。」
坂本「なるほど。そうですか。面白いなぁ。黒沢さん。」
黒沢「いやぁやっぱすごい映画だと思いました。あの、皆さんいかがだったでしょうかね。あの、やっぱり最初、わー綺麗だなーと、キラキラしていて思うんですけど。水の中って綺麗だなと思うんですが、だんだん、いやどうもここでいっぱい人が死んでるっていう情報が入ってきて、するとだんだん怖くなってくるんですよね。これ、死体か何か映るんじゃないのかっていう。で、だんだん水の底なんかに行くと、ますます怖くなってきて、ただ最終的にやはり、そのたくさん死んでいるけども、そこでマヤ文明……それが西洋の侵略によって滅ぼされた。でも、自分たちは生き続けているといったような最後のナレーションで……暗い湖底でも、まぁ魚たちが生きていたりして、何かこの、死だけではない、うん、そこでちゃんと生きているものもいるんだな、というところに、本当に見事に結びつけてるなぁと思いました。えーと、それで……音すごいですよね。コボコボコボって。まぁ水の中で、本当に僕自身、水に潜ったことがないので分からないんですけど、水中だとなんとなく聞こえてきそうな、コボコボコボっていう音がしてるかと思うと、なんか突然人が叫んでいるような音とか。で、いちばん印象的だったのはね、多分、そのここでいっぱい人が死んでるとかいうなことも、後半ですけども、暗い中にカメラが入っていって180度、その時はコポコポコポとかいう音しかしてないんですけど、カメラがギューンと180度向くと、向こうは明るくなっていて人が泳いでいるのかな、と思ったら、突然なんか人の叫び声だかなんだか分かんないんですけど、ものすごいノイズが……ちょっとゾッとするようなノイズが入ってきて、ちょっとするとパンと切り替わって、現実というか、あれも現実と言っていいのか。墓場で人がこう、骨を洗っていたりするショットになって、そこはあからさまな死のイメージなんですけど、もちろん向こうですから、割と陽気な現地の管楽器の演奏が聴こえてきて、いや、ハッとするんですよね。あの、明らかな死のイメージと、そこにしかし何か生きている感じとかが画面と音であれだけ……ある種の恐怖と共に表現されているのに、大変驚きました。で、すみません。長々と感想を言いましたけど。あの、サウンドデザインもご本人の名前でやってらっしゃったんですけど、まずどれぐらい手間をかけて、で現実の水中の音って僕はよく分からないんですけども、水中の音……それに何か付け加えたり、どれぐらい手間をかけて、どれぐらい色々加えたりして作られたんですか。」
小田「はい。音はですね、基本的には水中の音は、私は水中はiPhoneで撮っていたんですが、iPhoneが録音した同録の音です。タンクを付けて潜っている時には、ハウスみたいなのに入れてやっているので、それがカバーされて録音されてるって感じになります。それプラス、私のアシスタントでもあるし、現地の友人でもあるマルタのアシスタントでもあった人が環境音を録音してくれてて、そこからいくつかピックアップして、私の作業的にはコラージュのような感じでタイムラインにのせたり外したりして作っていきました。」
黒沢「基本的にはやっぱり全部、現地で録った、生でいろいろ録った音が組み合わされてるってことなんですね。」
 小田「そうですね。」
小田「そうですね。」
黒沢「なるほどね。」
小田「叫び声のようなやつは、熱帯雨林の保護区があったんですけど、そこでホエザルっていう……」
黒沢「あぁ、人間じゃないんですね。なるほどね。それであんなものすごい。あ、ホエザルかぁ。」
小田「でも、ホエザルの声を真似てる人間の声も入ってます(笑)」
黒沢「そうですか。これは、なるほど。」
坂本「はっはっは(笑)」
小田「ホエザルを呼ぶ為に、やってくださってて。」
黒沢「なるほど、なるほどね。僕自身がドキュメンタリーを撮ったことがないので、あまりよく分からないんですけども、今回のも、撮り始めていつ終わるんですかね(笑)。つまり、フィクションですと脚本というのがあって、1ページ、シーンいくついくつとかあって、一応最後までいったら終わりっていう風になったり。或いは、俳優がいると、その俳優のスケジュールとかですね、いろんなことで、終わりはここっていう、終わらざるを得ないとか、いろんな問題もあるんですけど、終われるんですけど……撮り始めて、これぐらい撮ったらもう十分かなとか、どっかで判断をつけるものなんですか。」
小田「そうですね。自分の場合は……一本出来るかなっていう気持ちになる時、まで、撮影するという感じです。」
黒沢「これえっと、3週間とかで十分、これで画は撮れた、とある時思って終わるっていう感じですかね。」
小田「今回の場合は、最後、魚の暗いショットでかぶせてる男の人のナレーションがありますけど……」
黒沢「はい、マヤ文明に関するナレーションですね。」
小田「はい、彼の声を録音させて頂いた時点で、あ、出来るかなぁっていう風に思いました。」
黒沢「あ、なるほどね。なるほど。」
荒木「大島さんの話に移りましょうか。なんか、小田さんはこの賞が決まってから、全ての作品を見直されたということでね。」
小田「ほぼ。3〜4作品、ちょっとアクセスが出来なかったのがあって、それ以外は全部見直しました。」
荒木「ね、小田さんからお二人にお伺いしたいことをぜひ。」
小田「音楽、戦メリ(戦場のメリークリスマス)……どういう風にコミュニケーションがあって、あの音楽が生まれたのかなって。」
坂本「その前に、その大島作品をほぼ全部観ていくと、戦メリだけすごく浮いてなあい?」
(会場・笑)
坂本「(笑) 戦メリが、僕の映画音楽の初めての経験だったんです。それでそれも最初、大島さんは僕に、「出演をしてくれ」と。はい、もちろん喜んで!というつもりだったんですが、何を間違ったか、「音楽は僕にやらせてください!」と言ってしまったんですよね。全く経験ないのに。そしたらその場で、「お願いします!」って言うわけ。その場で快諾するっていうのも、随分勇気のあることだなぁと思って。なかなかできないでしょう、黒沢さん。」
黒沢「いや、えっと、まぁそう……でも、坂本さんだったらね。いや多分、大島さんだったら、いかにもという感じですね。そら売れそうだ、みたいな(笑)打算もあって、そりゃきっと話題になる、って多分思ったんじゃないかなと思います(笑)。」
荒木「勘の鋭い人ですからね。」
坂本「もしかしたら、そのデヴィッド・ボウイと坂本がコラボして、歌が世界的にヒットするかもしれないと、即座に。」
(会場・笑)
黒沢「多分、あの、いやかなり、それ期待してた……この人音楽やってくんないかな、と思ってたんじゃないかな、とさえ思いますが。すみません、勝手なことを。」
坂本「(笑) そこからやり出して、やり方も分かんないの全然。技術的なことも。勝手にやっててですね、2〜3ヶ月かかったんですけど、その間に、ちょうど真ん中のあたりだったかな、大島さんが1回、僕が作業しているスタジオに訪ねてきて、それまで作ってる分をバーっと聴いて、「あいいです。続けて。」ってまた帰っちゃって。それでいよいよ完成して、持っていって全部聴いてもらって、もう100%全部、僕が作ったものを全部使う。そういうことって珍しいじゃないですか。」
黒沢「いや、まぁ、いや……でも、もう十分ありそうな。えぇ。僕もどちらかというとそれに近いかもしれませんね。いや、ま、あの音楽は僕はわりに好みがはっきりしていて、いろいろ口出したりするんですけど、この人を信頼したとなったら、大抵もうおまかせで、もう何やっても全てOKにしちゃいますね。」
坂本「いいですねぇー、もう……」
荒木「え、それ以来もうそういう体験はないんですか?」
坂本「えーほぼ2度となかったですね。完全にビギナーズラック(笑)。こんなもんだと思うじゃないですか。やった!みたいなね。この調子でやっていけるんだ、と思って。で、次の仕事映画音楽の2作目受けたら、すごい注文だらけで(笑)。直しとか、えー!? みたいな感じで。やっと。だから今も本当、直し続けて40年ですから(笑)。」
荒木「もう40年経ったんですねぇ。」
坂本「ほぼね。」
荒木「戦メリからね。」
坂本「83年の公開か。ほぼ40年近く経つね。まぁそんななんですけど。で、まぁ一人でコツコツと作っていて、その頃はもちろんMacもないし、その結局音楽と時間の尺のテンポとかの関係って、ちょっと数学的じゃないですか。それ、もう本当に手で、計算機で計算して、ここは何分何十秒だから、テンポが78だとすると、何小節と何拍になるから…とかってさ、そういうものを手作業でやってましたね。」
荒木「黒沢さんもやってみたらどうですか。」
黒沢「いやいや。あの、それ聞くと、それはそれで大変でしょうけど、羨ましいですね。日本でどうやってるかっていうと……こんなの参考になることか分からないですけど、日本ですと僕なんかやるのは、ある程度そうやってここからこんな感じ、ここからここまでこんな曲とかって作ってもらって、でも、ちょっと編集で変わったりするんですけど、ある程度作ってもらったら、あとはこっちでやりますって、全部引き取って、その専門家がせっかく作って頂いた曲を切り刻んで、今デジタルですから簡単に出来るんですね。まぁそういうことがありますよ、と最初に伝えてあるんですけど。で、ベースラインだけ別に録ったバージョンとかいろんなバージョンを作っといてもらって、うまーくやって、こっちの編集なりこっちの意図に合わせて……勝手にこっちがやっちゃうんですよね、ええ。作曲家の人の意図を無視して。」
荒木「最後の最後にしわ寄せが来るんですよね、音楽に。時間的に。」
黒沢「そうですね。それはもう本当は何度もそういうやりとりが出来たらいいんですけど、その時間もお金もないので、すいませんけどあとはこっちで、ってことで。それも多分、作った方は悲しいことだろうなとは思うんですね。」
坂本「そうですね。あの例えば、ドアを開けて誰かが、コツコツと歩いていって、ベッドに寝てる女性にピストル抜いて、バンと撃つと。その間、11秒と15フレームだとする。そのピストルまでがね。で、その音楽を付けてくれ、としますよね。書いていって、テンポはこのくらいかな。こういう弦の感じかな、と書いていって。ピストルの直前で、0.5秒ぐらい前で、音楽はもうバッと止まりたかったりしますよね、そう書きます。で、録音もします。で、持ってったら、「あ、ごめんごめん。それね、あの、8秒4フレにしちゃったから。」って言われると、もう全然ダメなわけですよ(笑)。でもね、映画人ですね、映画のやってる方は音楽も切れるもんだと、つまりフィルムっていうのは切って繋げても成立しますよね。ここんとこちょっと長いから、何秒何フレつまんじゃおうって。バシャっとつまんじゃっても、成立するけど、音楽の場合には、音楽の文法があって、フィルムと同じようにつまんで繋げちゃうと、もう構造が壊れちゃうっていうかな。そういう音楽もあるわけですよね。ま、そっちの方が多いわけですけど。で、つままれちゃってもいいような風に作ることもできます(笑)、あらかじめ。どこで絞ってもらっちゃってもいいような風に作るとかね。ただ普通に僕らが思っている音楽ってこう、テンポがあって、例えばある小節の3拍目の裏からいきなり切れてですね、11節目の2拍目に繋がったりしたらね、音楽がもう壊れちゃうわけですよ。もうメロディーも壊れちゃうし。それがね、どうもお分かりになってない……」
(会場・笑)
坂本「映画人の方がね、世界的に多いんですよ(笑)。いやまぁ、それはね音楽の事情なので、それ分かれっていうのもね、おこがましい話。実はね。だから映画音楽と通常の音楽はやっぱり違うんだと思うんですよ。それに対応していかなきゃいけないんです、こっちもね。」
荒木「じゃあ、今のところは、えー太文字で、報道の方よろしくお願いいたします(笑)。」
坂本「(笑) でも音楽っていうかね、まぁ音も全部自分でサウンドデザインやってるんで、そういう苦労はないですよね。」
小田「そうですね、いまのところ。」
坂本「自分以外の人に、音楽だけ以来したってことは今まではないんでしょうかね。」
小田「音を作って頂いたことは、短編で1作だけあります。」
坂本「あ、そうなんですね。その時はどうでした、望んでたものがきたって感じですか。」
小田「うーん……何を望んでいいのか、よく分かってなかったです。依頼した時に。なので、頂いて「あ、こういうのが出来るんだ」っていう風に、その時は思いました。」
坂本「じゃ、わりと新鮮だった?」
小田「そうですね。」
坂本「じゃ、結果良かったんですね。うんうん。」
 荒木「いろいろと、お悩みをお抱えのようで(笑)今回の大島渚賞、これからも毎年続けていくということで、来年も小田さんと並ぶ、素晴らしい人を見つけて頂かなくていけないお二人なんですけど。」
荒木「いろいろと、お悩みをお抱えのようで(笑)今回の大島渚賞、これからも毎年続けていくということで、来年も小田さんと並ぶ、素晴らしい人を見つけて頂かなくていけないお二人なんですけど。」
坂本「難しい……」
黒沢「新人でないとまずいんですかね。僕、対象にならない?」
荒木「え、審査員であり、受賞者ですか?」
黒沢「いやいや。」
坂本「それありですか。」
黒沢「新人しかダメなんすかね。」
荒木「それは皆さんのこれからの反応によって、考えていきたいと思いますが。えー、大島渚賞は、本当にこれからも続けてまいりますので、どうぞみなさん、小田さんのこのあとも見守って頂きたいですし、大島渚賞も見守って頂ければ嬉しいです。今日は長い時間、お付き合いありがとうございました。えー、坂本さん、黒沢さん、小田さんありがとうございます。そして小田さんにお祝いの拍手をどうぞお願い致します。」


<坂本龍一 「この2ヶ月で聴いた曲から紹介」プレイリスト>
「ここからはね、僕がこの間、聴いてきた音楽……今も聴いているかな、のプレイリストをやりましょうね。何を聴いてきたかな、僕はね。そうですね。あの……アイスランドのJónsiっているじゃない。ボーカリストですよね。彼はやっぱコロナウィルスに感染したらしいんですよね。で、それで帰還した、治って出てきたそうなんですよ。それで作ったのが「Exhale」っていう、シングルかな、これね。」
「はい、えーっと、90歳だったかな……あの、Lee Konitzという、大御所の大御所の大御所ぐらいのそのジャズサックス奏者がいるんですけども、残念なことにコロナウィルスに感染して亡くなりました。追悼の意味も含めて聴いてみましょうね。とっても有名な曲で、今の世界中ね、ロックダウンして外出自粛してるわけですね、みんなね。世界中が、何億人もが。ま、それに相応しい曲といったら変ですけども、「Alone Together」という。」
- Alone Together take 1 / Lee Konitz & Antonio Zambrini(『Atone & Together, Chapter 3』)
「まぁあの、どうしても緊張状態ではありますよね。気持ちがね、精神が。こういう時ってね、やっぱり耳に入ってくる、気持ちに入ってくる、聴ける音楽ってのはなかなかこう、絞られてきますね。そんなたくさんないんですよね。で、僕の個人の気持ちから言うと、やっぱりどうしても宗教曲みたいなものが多くなるんですね。で、前にも以前にかけたことがあるんですけども、20世紀に入ってからのフランスの、現代の作曲家でMaurice Durufléという人がいて、作曲家でもあり、それからオルガン奏者でもあって、実際、教会で弾いていた人でもありますけども、このね、Durufléさんのいちばん有名な曲と言ってもいいかな、その「Requiem」というのがあるんですけども、やっぱり前もかけたかな。でも聴いてみましょう。」
- Requiem: II Kyrie / Maurice Duruflé(『Duruflé: Complete Choral Works』)
「はい、次はですね、日系のアメリカ人のヴァイオリニストでとっても上手い人なんですけど、Anne Akiko Meyersという人がいるんですけど。これ僕あの、えっと311の災害があった後に、その日本を応援するというコンサートがあって、Laurie AndersonとかLou Reedとか出てたんだけど、そのときに僕は、このAnneさんと二人で一緒に演奏で出ました。その彼女が弾いている、Piazzollaですね。あの、アルゼンチンタンゴの。Astor Piazzollaの曲をヴァイオリンとピアノでやっています。『Smile』というアルバムからです。」
- Astor Piazzolla Introducccion Et Angel / Anne Akiko Meyers(『Smile』)
「では最後にね、えーとこの間僕が聴いてきて、いちばん……なんか今の気持ちにぴったりくる、でこれやめられない(笑)、やめられない感じなんですけど。あのね、全然僕知らなかったんですね、この人のこと。えー、僕より少し年上のドイツの作曲家……現代音楽の作曲家が、異常になんかポップな曲作っていて。えーこれは、「Organum: IV. Part 4」なんですけど、Peter Michael Hamelという。」
- Organum: IV. Part 4 / Peter Michael Hamel(『Hamel, P.M.:Organum』)

<デモテープ・オーディション>
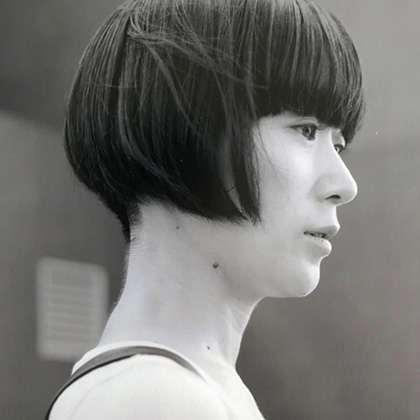
U-zhaan「レディオサカモト。ここからは僕U-zhaanと……」
長嶋「長嶋りかこ、そして……」
坂本「坂本龍一、フロム・ニューヨーク。」
長嶋「(笑)」
U-zhaan「の、3人でお送りしていきます。えーこのコーナーはアレですよね、もう4年前からずっとテレワーク状態というか、教授がニューヨークで、こちらが東京、J-WAVEから。」
坂本「僕だけテレワークだったんですね。」
U-zhaan「はい。だからもう慣れてるんですけど。」
坂本「いち早く、世界に先駆けて。」
U-zhaan「今回から、全員が自宅という。」
長嶋「うん、初めて。」
坂本「この方がいいじゃんっていう話に。」
U-zhaan「何でこっちの方が音いいんでしょうね。」
坂本「音もいいし、なんかやりやすいよねっていう。」
U-zhaan&長嶋「(笑)」
U-zhaan「そうですね。教授だけ一人だったからなんかあの、ちょっと僕らが隣でっていう、違和感は少しあったけど、今回全然違和感ないですもんね。全員が一人ずつって。」
坂本「なんか自然光が入って、すごく良い感じですよ、光が。」
長嶋「あ、本当ですか?」
坂本「こっち今、夜なんで。」
U-zhaan「そうかそうか。」
長嶋「そうですよね。」
U-zhaan「教授は何をしてらっしゃいますか?最近は。」
坂本「お酒を飲んでいます。」
U-zhaan&長嶋「(笑)」
坂本「あ、今ね、今。ご飯食べちゃったんで、飲んじゃう。」
長嶋「あ、たった今ですか?」
坂本「はい。」
長嶋「たった今?」
坂本「いや、もう…」
長嶋「なんか、ちょっとハイだなとは思った(笑)」
坂本「ちょっと2杯くらいからいきましたけど。」
U-zhaan「いいですね〜。」
長嶋「いいなぁ。」
U-zhaan「そして、あれですね、今、放送されているドラマ『きょうの猫村さん』の主題歌を、教授が作曲で、僕が作詞で作っているんですけど。なかなか楽しい作業でしたね、あれもテレワークで、ニューヨークとインドで制作していたんですよね。」
 長嶋「インドで。そっかそっか。」
長嶋「インドで。そっかそっか。」
坂本「あと、松重さん本人が歌っているという。」
U-zhaan「あぁそうですね。」
長嶋「へぇ。」
U-zhaan「主演の松重豊さん。で、松重さんが猫村さん役っていうのも、とんでもないんですけどね。教授、番組観ました?」
坂本「観てますよ。でかいんですよ。」
U-zhaan「でっかいですよね。番組が2分半の番組なんですけど。」
長嶋「あ、そんなに短いんだ!」
坂本「1週間に1回なの。」
U-zhaan「主題歌が3分くらいあるんで。初回しか流れないっていう主題歌。もう通しては流れないですけど。」
長嶋「え、マジで(笑)。どうやったら聴けるんだろう。」
U-zhaan「今日流そうと思います。」
坂本「全部観た?U-zhaan。」
U-zhaan「あ、僕は2回目まで観ましたね。」
坂本「あ、僕もう全部観たよ。」
U-zhaan「あ、最後まで観たんですか?」
坂本「うん。」
U-zhaan「あ、そうなんですか。僕はそんなあの、観ますか?とも言われてないですね、やっぱり。」
坂本「特権で。」
U-zhaan「特権が。僕には全然特権来てないですけどね(笑)。」
坂本「文句言った方がいいんじゃない、それ(笑)。」
U-zhaan「僕……めちゃくちゃ(笑)、松重さんのボーカルの入れるのも立ち会ったし、マスタリングまで行ってるのに全然来てないですよ。」
坂本「特権が(笑)」
長嶋「頑張ってU-zhaan。」
U-zhaan「夜中起きて観てください、みたいな感じでしたよ。」
長嶋「アピールして(笑)。アピールアピール。」
U-zhaan「大丈夫です。僕控えめなんで。観ます。夜中に観ます。」
坂本「控えめ(笑)」
U-zhaan「では、やりますか。」
坂本「はい、じゃあお願いします。」
U-zhaan「今回、300作品ぐらい応募があったみたいなんですけど、めちゃめちゃ多かったですよね。」
坂本「多かったです。選ぶのも大変でした。」
U-zhaan「聴いても聴いても終わらない。」
坂本「終わらないです。」
U-zhaan「力作揃いで、楽しかったですけどね。ものすごい時間がかかりましたね、聴くのに。」
長嶋「みんなやっぱお家にいると、作りたくなる感じなんですかね?」
U-zhaan「ね。やっぱこの、今の状態に感化されて作った曲みたいのもいっぱいありましたしね。」
長嶋「あぁ、そうですね。」


RADIO SAKAMOTOオーディションに、インターネットから作品を応募できるフォームができました。作品はファイルのアップロードのほか、YouTubeのURLを指定しての投稿も受け付けます。
詳しくは、エントリーフォーム内の応募要項をお読みください。
 |
|

|
RADIO SAKAMOTOオーディションに御応募頂いたデモ作品にまつわる個人情報の管理、作品の管理は、J-WAVEのプライバシー・ポリシーに準じております。詳細は、こちらを御確認ください。 |
|

<エコ・レポート (more trees 水谷伸吉)>

「皆さん、こんばんは。more treesの水谷伸吉です。今、新型コロナウィルスの影響が全国各地に出てると思うんですけれども、僕ら森作りの活動している団体としては、ぜひ『STAY HOME』、お家に籠もりながらも自然とバーチャルだけれども触れ合う、そんなきっかけをご紹介したいと思います。例えば、僕らもそうですけれども、森林とか自然の美しい画像、これをスライドショーで公開しているんですけども、そういったものをご覧頂くだけでもですね、現地の美しい自然とバーチャルで向き合うことができるんじゃないかなと思いますし、もちろん写真だけじゃなくて、動画とか……森を感じれる自然を感じれる美しい動画はいっぱいありますんで、ぜひYouTube等でも色々出てると思いますから、そういうのを探してみて頂く、もしくはモニター、テレビにね接続すると、より大画面で感じることも出来ると思いますんで、そういっただけでも、自然とバーチャルで繋がることができると思います。あとは、僕らだと、宮崎県の諸塚村。実はそこに、とある会社さんがマイクを設置していて、そこから森とか自然の音がリアルタイムで配信出来る、そんなサービスがあるんですね。で、それをリアルタイムでキャッチすることで、ご自宅でも鳥のさえずりとか、あの、風が吹いて葉っぱが擦れる音とか、そういった音が自宅にダイレクトに届けることが出来ますので、そういった音をですね感じながら、ぜひお家の中でも癒やされてみてはいかがでしょうか。ちなみにこの『STAT HOME』の企画、僕らmore treesのWEBサイトでもいろんなコンテンツをご紹介していますので、ぜひご覧になってみてください。」
「森に直接行くだけじゃなくて、例えば、お子さんと一緒に木工を家で試してみる。そういっただけでもですね、結構楽しめると思うんですね。例えば、木で椅子を作るキットとかスプーン作るキットっていうのも、ネットでも販売されてますので、そういったもの買ってみて、親子で試してみるとか、お子さんの手を動かす、そんな場にしてみても面白いかもしれません。もちろん大人でも日曜大工やるとかですね、DIYでこの際、試してみるとか、そういったことでも十分、木に触れ合ういいきっかけになるんじゃないかなと思います。今後、新型コロナウィルスが必ず事態は終息するわけですけれども、その後やっぱり、これまでとはちょっと違う価値観というのが生まれてくるんじゃないかなという風に思っています。例えば、テレワークとかもそうですし、やはりこのバーチャルとか、デジタルとかっていう部分が更に発達してくる、そんな気がしています。そういった中でも、森林って非常にアナログですが、やっぱりその森林とか自然が果たす役割というのは非常に大きいと思うんですね。なので僕らは、まずは粛々と森作りを進めていくということと、あとはやはりそのバーチャルとかデジタルっていう力も借りながら、より森の魅力を都会の人に……遠隔の人にも伝わるような、そんな工夫も考えていきたいなぁと思っています。以上、水谷伸吉がエコ・レポートお届けしました。」

|

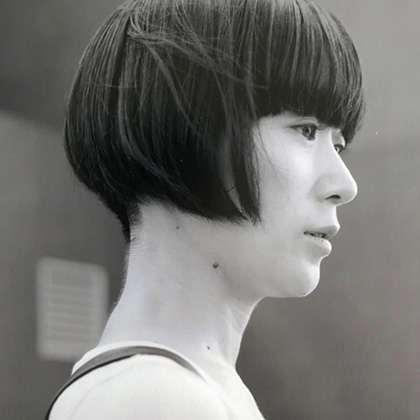



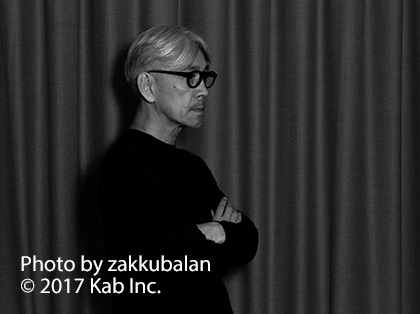 「4月の頭頃にニューヨークに帰ってきて、その頃っていうのは、まだピークに向かっていた頃かな。ピークが確かね、15日ぐらいだったと思うんで。まだまだ、どんどん感染拡大してるニューヨークに帰るっていうのはどうなのか、随分周りに反対されましたけどね、実はね(苦笑)。あの心配してくれたわけですけど、みんなね。あんまり人がいないところに、道に来いとかっていう有り難い話も頂いたんですけど、あの……まぁ、日本にいてね、東京でホテルに泊まってるんですよ、家がないんで。それもちょっとプライバシーの話をしちゃいますけども。で、ホテルに泊まってる。で、万が一、東京で僕が感染して熱が出たら、ホテルが困るんで追い出されちゃうわけですね。で追い出されて、じゃああの短期で急遽マンションを借りる、これもやっぱり熱が出てる人は貸してくれないわけですね。で、路頭に迷う、もし感染したら。でもう僕は、発表される感染者数、数っていうのは全然信用してなくて。結局その、当初はクラスター対策うまくいっていますって言ってましたけども、発表では、僕は全然信用していなくて。まぁ確かにクラスターで追っかけられた部分もあるでしょうけども、それをやってるうちに、市中感染、見えない街なかの感染がどんどん広がっているに違いないと僕は確信していたので、でそれは今となっては事実というかね、クラスター対策班の専門家の方達が、事実上、うまくいかなかったというようなことも認めてらっしゃるそうですけども、僕は見えない市中感染がひどいと思っていたので、日本にいても、ニューヨーク州の方針になるべく沿ってですね、行動してたりとかして。でもまぁ本当に分かりませんから、日本にいて感染するかもしれない。そしてもうどこにも行きようがないっていうんで、どうせ隔離生活するんだったらば、やはり自分の家でしたいよねっていうんで、まぁあの、本当に結構……決断してニューヨークに帰ってきた。で、ニューヨークは感染がまだまだ拡大している途中で、本当に1歩も出ないで、かなり緊張状態ではありましたね、やっぱりね。で、今の状況でいうと、だいぶピーク時からは下がってきて、いろいろな死者数とかですね、新しい日毎の感染者数とか、入院者数とかですね、それぞれの数字がどんどんどんどん下がってきてはいますけども、それでもまだ一日に300人以上の方が亡くなってるというのが、本当にそれでも異常事態ですよね、一日ですからね。いやぁ、でもこの話はキリがないですね、すいません。」
「4月の頭頃にニューヨークに帰ってきて、その頃っていうのは、まだピークに向かっていた頃かな。ピークが確かね、15日ぐらいだったと思うんで。まだまだ、どんどん感染拡大してるニューヨークに帰るっていうのはどうなのか、随分周りに反対されましたけどね、実はね(苦笑)。あの心配してくれたわけですけど、みんなね。あんまり人がいないところに、道に来いとかっていう有り難い話も頂いたんですけど、あの……まぁ、日本にいてね、東京でホテルに泊まってるんですよ、家がないんで。それもちょっとプライバシーの話をしちゃいますけども。で、ホテルに泊まってる。で、万が一、東京で僕が感染して熱が出たら、ホテルが困るんで追い出されちゃうわけですね。で追い出されて、じゃああの短期で急遽マンションを借りる、これもやっぱり熱が出てる人は貸してくれないわけですね。で、路頭に迷う、もし感染したら。でもう僕は、発表される感染者数、数っていうのは全然信用してなくて。結局その、当初はクラスター対策うまくいっていますって言ってましたけども、発表では、僕は全然信用していなくて。まぁ確かにクラスターで追っかけられた部分もあるでしょうけども、それをやってるうちに、市中感染、見えない街なかの感染がどんどん広がっているに違いないと僕は確信していたので、でそれは今となっては事実というかね、クラスター対策班の専門家の方達が、事実上、うまくいかなかったというようなことも認めてらっしゃるそうですけども、僕は見えない市中感染がひどいと思っていたので、日本にいても、ニューヨーク州の方針になるべく沿ってですね、行動してたりとかして。でもまぁ本当に分かりませんから、日本にいて感染するかもしれない。そしてもうどこにも行きようがないっていうんで、どうせ隔離生活するんだったらば、やはり自分の家でしたいよねっていうんで、まぁあの、本当に結構……決断してニューヨークに帰ってきた。で、ニューヨークは感染がまだまだ拡大している途中で、本当に1歩も出ないで、かなり緊張状態ではありましたね、やっぱりね。で、今の状況でいうと、だいぶピーク時からは下がってきて、いろいろな死者数とかですね、新しい日毎の感染者数とか、入院者数とかですね、それぞれの数字がどんどんどんどん下がってきてはいますけども、それでもまだ一日に300人以上の方が亡くなってるというのが、本当にそれでも異常事態ですよね、一日ですからね。いやぁ、でもこの話はキリがないですね、すいません。」 小田「そうですね。」
小田「そうですね。」 荒木「いろいろと、お悩みをお抱えのようで(笑)今回の大島渚賞、これからも毎年続けていくということで、来年も小田さんと並ぶ、素晴らしい人を見つけて頂かなくていけないお二人なんですけど。」
荒木「いろいろと、お悩みをお抱えのようで(笑)今回の大島渚賞、これからも毎年続けていくということで、来年も小田さんと並ぶ、素晴らしい人を見つけて頂かなくていけないお二人なんですけど。」 長嶋「インドで。そっかそっか。」
長嶋「インドで。そっかそっか。」